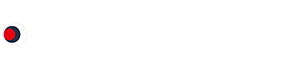図書
『令和版剣道百家箴』
「一生の修業を念じて・・・」

剣道範士 笹月 繁(大阪府)
「箴言について述べよ」とのことであるが、私には箴言などと言えるものは無い。85歳の人生の中で、特に剣道をとおして得たもの、思うことを述べて、これに替えさせて戴きたい。私は高等学校教員(保健体育)としての23年間、46歳から14年間に及ぶ管理職時代(教頭6年、校長8年)の勤務をとおして、様々な経験をして来た。教員としては、東京で私立高校、大阪に転じて大阪市立の商業高校、大阪府立の普通科高校で勤務。それぞれ設置者が異なり、実業高校、大学進学者多数の高校、と生徒の進路も多様な学校での勤務であった。特に大阪市立の商業高校については、設立間もない大阪市立修道館少年剣道指導係との兼務、という辞令であった。指導の対象者は多様であるが、体育の授業、剣道部での指導等を通して得たことがある。それは「生徒に学ぶ」「生徒の長所を見つけ、これを伸ばす」ということである。
「生徒に学ぶ」とは何か。生徒が学ぶ時に見せる反応は、私の指導に対するもの。私の指導を理解し、心地よく受け入れているかどうか、を示すものであり、それは私の指導力を表したものと思われるからである。「長所を伸ばす」とは、私達指導者のあり方についてである。私達指導者は、ややもすると、先ず指導対象者の「欠点」を見つけて、その矯正を行うことが多い。「ここが悪い」「ここを直せ」等々である。指導を受ける者は、「欠点を直す」ことに縛られ、長所が隠れてしまいかねない、と思われる。私は、先ず「長所」を褒めて認め、ここ(欠点)を直せばもっと良くなるよ、といったやり方もあるのではないか、と考える。何れにせよ指導相手の示す反応は、私達指導者の指導力を映す鏡のようなものではないか。日頃の稽古においても、相手に学ぶことは少なくない。私達指導者が心すべきは、常に相手に学ぶ姿勢であり、「我以外皆師」という一つの箴言に通じるものではなかろうか、と思われるのである。
次に、自分自身の修業のあり方について考えてみる。私の教員時代は、放課後の剣道部の稽古の指導と、週2日程度の修道館での稽古、という日々であった。然しながら、定時制高校の教頭となって3年間、全く稽古が出来なくなってしまった。次の3年間は全日制普通科の高校での勤務。ここでは、国旗・国歌に関しての問題と向き合うことになった。当時法制化された式典等における、国旗の掲揚と国歌斉唱の実施について、これを阻止しようとする教員集団との問題であった。国旗掲揚柱をめぐって、校長・教頭と彼等との文字通りの肉弾戦を演じることなど、剣道家の皆様には想像もつかないことであろう。またこの学校は大阪の中心地より遠いため、勤務後の道場通いも難しかった。既に八段受審年齢(当時48歳から)に達していたが、稽古不十分の身では、と考えて断念した。校長職となっての5年間も、全日制・定時制併置校の勤務辞令であり、道場通いなど公に出来なくなってしまった。この時、52歳。友人・知人達の「八段合格」の報に接することが多くなった。然し、私自身はこの状態での八段受審などあり得ないこと、と断念し、定年退職後、相応の稽古をして挑戦すると明確な意志決定をしていた。八段受審へ向けて何をすべきか。道場へ行けない今、どうあるべきか、を考えた。校務に支障のない範囲で、校長室での素振り、中段に構えて足捌き、相手の動きを想定しての体捌き、等々を行うことで、剣道への復帰、八段への挑戦に備えた。残る3年間は、平穏な全日制高校勤務になり、時折り剣道部の稽古に参加したり、勤務後道場に寄るなどで、徐々に「剣道の世界」への復帰につながったように思われる。
定年を迎えて本格的に稽古が出来るようになり、61歳から愈々八段審査を受け始めることになった。私は、七段までは総て1回の受審で合格を戴いて来たが、「八段」の厳しさは知っていたので覚悟はしていた。やはり厳しい結果となった。以後京都での審査を中心に、東京での受審を含めて20回を超え、合格を認められたのは74歳の秋であった。振り返って思うに、当然のことながら稽古の大切さであり、心構えである。校長室での一人稽古も意味があったのであろう。「至るところに道場あり」とでも言えようか。日曜日の町の子供達との剣道教室、修道館での高段の皆さんとの稽古等々、全てが大切な修業の場である。「一生修業」を念ずる日々である。(受付日:令和7年5月23日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。