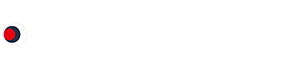図書
『令和版剣道百家箴』
「昇段に通じる理業兼備」

剣道範士 牧瀬 憲保(福岡県)
剣道を学び始めてから数十年、心身共に満ち足りた心境にはほど遠い。毎年、正月元旦に書き初めをするのが慣例だが、令和7年の元旦には、「この道未だ極めず 終わりなし この道を歩く」と揮毫した。
称号、段位こそ最高位を拝受したが、日頃の稽古の度に心を動かされる自分に情けなさが生じ、剣道というものの難しさを痛感している。
そもそも剣道を始めたきっかけは、幼年時代病弱だった私に亡き父から「お前は体質の改善が必要だ」「剣道をやりなさい」と勧められ、町道場に通い出したのが事の始まりである。中学、高校、大学と剣道を修行するにつれ、人並みに試合に勝ちたい、昇段したいという気持ちが次第に高まってきた。福岡県警に入り、25歳で剣道特別訓練員に任命を受け、厳しさを乗り越えた結果、指導者としての道が開かれ、今日までの剣道人生の基礎が出来たと自負している。やがて小生も79歳、これまでの体験を生かし、後輩となる剣道修行者に何か役に立ちたいとの思いでペンを握った。
そこで第一に上げたいのが、昇段審査に臨むにあたっての稽古のあり方や心構えである。剣道修行者にとって昇段審査、特に高段位(六・七・八段)に合格することは悲願である。合格するために私なりに経緯と対策を述べてみたいが、あくまで私見であることを理解していただきたい。
先ずは高段者には熟練度、鍛錬度が当然求められるが、それプラス「理合」、「風格」、「品位」が備わっていることである。「理合」の「理」は道筋、道理。「合」は一致する、調和するということ。審査においては、攻めや打突が筋の通ったものであるか、調和のとれたものであるかが問われる。無理、無駄、無法は違和感や不自然さが生じる。
「風格」の「風」はその人の姿・人柄から発し、人を動かす要素で、風貌、態度や言行に表れ、その人の味わいや趣きでもある。「格」は身分や位がきちんとしている事。不動心の訓えとして中国の「木鶏」の逸話がよく語られるが、まさに動じない姿である。
「品位」とは感覚的ではあるが、風雪に耐え抜いて咲いた梅の香りのイメージである。もちろん礼法や着装など、品位に直結する具体的なところは身に付けておくことだ。
「理合」「風格」「品位」は、日頃の実直な取り組みを通じ、その人の剣道に備わってくるものであるが、それらを身に付けるという意味でも大いに生かすべきは、私は「日本剣道形」であると思い続けてきた。「日本剣道形」は理合そのものであり、取り組めば取り組むほど風格、品位が備わり、加えて、剣道の悪癖が直る。
次に、攻防一致の剣道に磨きをかけるには、基本稽古を実戦的に行うことである。
有効打突の条件に「充実した気勢」「適正な姿勢」があり、「竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打つ」ことや「残心」が必要とされる。そこで日頃の基本稽古では、惰性でなく、一本一本、「有効打突の条件」を満たすように打つことで、基本動作を磨いていく必要がある。掛かる方と元立ちが息を合わせて約束稽古に取り組むことが効果的である。一年もすればかなりの蓄積となり、お互いに攻防一致の剣道が進歩していくことは間違いない。
また攻め合いでは、「剣を殺す」「気を殺す」「技を殺す」といったことを具体的にイメージするだけで身の入れ方は違ってくる。「百錬自得」。観衆にも感動を与える「心に響く打突」が体得出来るだろう。
3つ目は蹲踞から立ち上がったら、気を丹田に収めるような冷静さが欲しい。
我が道場は「気を溜め、身を捨てる処」をモットーに稽古に励んでいるところであるが、大事にして欲しいのは、「気の溜め」である。蹲踞から立ち上がったら、「自分の心がどこにあるか」、「しっかり丹田に納まっているか」ということを感じられるくらい冷静であっていただきたい。腹に気を溜め、胆力をもって、攻められたら攻め返す。しっかり腹や腰を意識して攻め返す。そうして機会をつくったら、身体ごと乗せていくように打ち切ること。そして最後の残心まで気を抜かないこと。そこまでのストーリーを作ることはやはり、気の溜めがいかに大切かということである。
県内等で開催される受審者講習会での講師としての資料を、自分なりの体験から以下のように作成した。
受審についての心構え
①審査はもう始まっている
・審査日に照準を合わせ、長期計画のもとで稽古に励み、心身の鍛錬・調整を図る
・酷暑、酷寒の中での修行が、やがて、いい香りで実を結ぶ
・継続は力なり
②謙虚で平常心で審査に臨む
・礼法をおろそかにせず、節度を持って審査に臨む
・剣道着、袴、および防具の着装が修行の年輪を物語る
・竹刀は魂(刀)と思って取り扱う
・今までの修行を見てもらいます。謙虚で透明な心で
③胆力を捉える
・丹田呼吸法(腹式呼吸)。心を腹の底に置く
・蹲踞から立ち上がった時、溜めがどこにあるか、丹田に納まっているか確認できる
冷静さを
④立ち合いは目の前の相手だけではない
・会場の雰囲気、審査員、全てを呑み込む大気
・審査員を注目させる気迫と充実した気勢
⑤合格への方程式はない
・相手に理論、理屈は通じない
・小手先だけでは相手の心は浮かせない
・勝った者が通る(合格する)
・克って後、戦う
大旨、昇段審査に臨む姿勢について述べてみたが、これも大河の一滴に過ぎない。能く能く研究、努力され成功されんことを祈りたい。
最後に山岡 鉄舟先生の言葉を紹介したい。
「剣道暦数十年、絶対不敗の境地まできた。そしていま、最後の難関を砕き去ったぞ。一点に集まる露のように満ちたりたこの平静」(山岡 鉄舟『剣禅話』)(受付日:令和7年5月2日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。