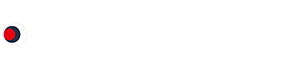図書
『令和版剣道百家箴』
「剣道と共に歩む我が人生」

剣道範士 尾方 正照 (熊本県)
私は八十路を迎えた。初めて竹刀を握ったのは小学3年生、10歳の時だった。ちょうど70年、剣道と共に生きてきたことになる。
高校卒業後、大阪府警察に奉職した。初めての大都会暮らし、慣れぬ勤務。心身ともに緊張の連続だった。しかし、どんなに疲れていても、剣道具を担いで大阪城内の修道館道場に向かった。剣道はいつも私を支え、励まし、応援してくれた。
5年後、郷里の熊本に戻ったが、全国大会や各種の大会、講習会、審査会などで、大阪時代に指導していただいた先生方をはじめ、先輩や元同僚と竹刀を交えるのは本当に愉しかった。少しでも進歩した姿を見ていただこうと、張り切ったものだ。
無論、人生は平坦な道ばかりではない。迷い、逡巡し悩むことも少なくない。が、道場の門をくぐる時、決まって私の心に浮かぶのは「八風吹不動」の言葉である。
利、衰、毀、誉、称、譏、苦、樂。人は得てして、利害、損益、風評によって揺れ動くものだが、動じない不動の心を持てという、禅の教えである。この言葉を反芻しながら、竹刀を握り稽古に打ち込んだ。心の葛藤は消え、雑念も拭い去ってくれた。
35歳から20数年間、少年剣道に携わった。勤務の後の少年剣道の指導は、帰宅の時間も遅くなり、土曜、日曜、休日も殆んど大会や錬成会で埋まったが、子供たちの一生懸命さと、保護者の皆さんの熱心さに、疲れも忘れた。
今は社会人になった当時の子供たちが、「尾方先生」と駆け寄り、昔の苦労話や近況を話してくれるのも嬉しい。また、自分は剣道をやって良かったと、我が子を道場に通わせている教え子も多い。
現在は、熊本学園大学剣道部の師範として指導し、剣道連盟の土曜稽古会、社会人の稽古会で汗を流している。社会人の中には60代後半、70代の方も多いが、皆さん実に熱心、意欲的で、私まで気持ちが若やぐ。まさに剣道は、私にとって人生の相棒だ。
しかし、近年は少子化に加え、コロナ感染症の影響もあり、青少年の部活動も球技に流れ、剣道の青少年人口が激減しているは焦眉の問題である。これについては色々講じられているが、今のところ特効薬はない。指導者、稽古場所(施設の問題・空調など)、時間の確保も大切ではないかと考える。道場が遠方で、稽古時間も日没後であれば、保護者の送迎など負担は大きくなる。地域で考えなければなるまい。
海外では剣道人気は高まっていると聞く。しかし、本家本元の日本で、日本人の心とも言うべき剣道人口が減少の一途を辿っているのは、なんとも残念だ。何としても食い止める方策を考えたい。
私の生まれた故郷近くに、「タイ捨流」の祖として知られる丸目 蔵人の生誕地がある。かつて全日本選抜剣道七段選手権大会が開催されていた、錦町である。また、熊本市近郊には、宮本 武蔵が五輪書を著したと伝えられる霊巌洞があり、熊本市内に旧居跡や墓がある。私は毎年元日の朝、霊巌洞に詣で、記帳するのが年頭の恒例行事になっている。
定年の60歳を2年残して、私は職を辞した。3日に1日は一昼夜勤務という勤めが続いていたから、元気で健康なうちに多くのことを学び、体験しておきたいと思ったのだ。美術展や刀剣展、コンサート、講演会、映画鑑賞、初めて識ることも少なくなかった。各地の城郭や史跡も百聞は一見に如かず、大いに勉強させてもらった。特に、鹿島立ちで知られる鹿島神宮を訪ねた折、塚原 卜伝もこの道を歩いたかと思うと心が弾んだ。巣鴨の千葉 周作の墓所を訪れたりもした。浅草の島田 虎之助の墓前では、「剣は心なり・心正しからざれば剣また正しからず…」と、若くして逝った虎之助の言葉を噛みしめながら、手を合わせた。
私は、剣道の盛んな九州熊本に生まれて、本当に幸せだった。剣道の道に進ませてくれた両親、教え導いていただいた師、大阪、熊本の剣友多くの方々のお蔭で、これまで続けることができた。感謝を忘れたことはない。
これまで
○竹刀に鍛えられ
○竹刀に励まされ
○竹刀に叱られ
○竹刀に育てられ
今がある。
初心を忘れず、感謝を忘れず、剣道発展のため、微力ながら力を尽くしたい。生涯剣道を全うし、剣道人口を増やせるよう頑張りたい。(受付日:令和7年5月23日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。