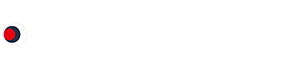図書
『令和版剣道百家箴』
師の訓え「話は目で聞け!」

剣道範士 藤原 崇郎(広島県)
アメリカを中心とした連合国軍の占領下におかれていたわが国では、それまで全面的に禁止されていた剣道がようやく復活できることとなり、昭和27年(1952)になって全日本剣道連盟の結成を見るに至った。
長崎市から100Km以上離れた東シナ海に浮かぶ“五島”で、昭和21年に生を受けた私が竹刀を持ち始めたのが6歳の頃。ちょうど全剣連のスタートと時を同じくしており、何かしら因縁を感じている。
父親も戦時中に剣道の心得はあったものの、私の師匠は馬場 武雄氏である。師は母方の祖母の弟にあたる。幼少の頃は、藤原家と馬場家が一つ屋根の下で同居していたために、馬場家の兄弟姉妹とは、兄弟同様の扱いを受けて育った。小学生低学年の頃の稽古と言えば、足さばき、構え、素振り、打ち込みの基本動作の反復がほとんどで、一番年少者という事もあって興味、関心が湧くこともなく義務的な道場通いが続いていた。中学生頃になると、後輩の剣士も次第に増え始め、師の指導理念「もののあわれを感じ 風流で 優雅さがあり 思いやりのある人間たれ」の想いが次第に浸透してきており、稽古も熱を帯びるようになってきた。その頃は道場での礼式が終わると決まっていささか長い訓話の時間となる。師は「剣道の日常化」について少年剣士へ熱く語り始める。
日常の生活において、物事への対処の仕方であるとか、考え方。判断を迫られる場面に出くわしたときに、剣道の精神と関連した捉え方を求める指導方針である。逆説的に言うと「剣道を如何に普段の生活の中に位置付けながら過ごしていけるか」という発想となる。その中でも私にとって強烈であった訓えの言葉が「人の話は目で聞け!」である。少年時代から幾度となく聞いていながら 「はて?話は耳で聞き取るのではないのか?」と自問自答しながら不思議な感覚に陥っていた。それでも絶対である師の言葉に実直でありたいという気持ちがそうさせるのか、反射的に正座している膝の向きが変わり始め、正対する態度が身についてきた。また、学校で先生の説明が始まると、下を向いていた顔がつい起き上がり、いつしか目と目を合わせて聞き入るようになり始めてきた。
「何処を向いていても話し声は聞こえてくるが、それでは話す人が何をどう訴えようとしているのか、その真意を汲み取ることはできないだろう。第一相手に対して失礼になる。」と、師の声が続く。
70年を超える長い剣道修錬の道のりではあるが、ここまで私の根幹を形成しているのは、まさしく「話は目で聞く!」習慣を積み重ねてきたことによるものである。故郷を離れて東京での学生時代を過ごした4年間。数多くの斯界高名な先生方と接する機会に恵まれた。緊張しながらも、剣道談義、人生の歩み方、考え方、対処の仕方などの体験談を拝聴させていただく瞬間は、実に楽しく、嬉しく、有意義な時間であった。まさに自己成長に繋がる貴重な機会であったことに気づくのである。聞こえてくる言葉は耳から入るが、語りかけてくる口調、表情、身振り、手振り、さらには姿勢、熱意、迫力など、目で受け止めるからこそ語り手の真意や人柄までを感知することができたのである。
武蔵の言う「目に見えぬ所をさとつてしる事」(『五輪書』地の巻)の訓えはあまりにも有名であるが「目付け」の本質を見事に捉えている。私なりの解釈をすれば「目付け」とは物事の本質を見極めるために、見えるものから見えないものを感知して、さらにその先を洞察していくところまで繋げることが要求されるのではないかと思っている。‟どこを見るか”でなく、‟どう見抜くか”という捉え方にまで昇華していくことだと理解している。
稽古における「目付け」もまさしくその通りである。正対している相手の視線から見抜く。その入り口は、一瞬でしかも微妙な変化(鋭さ、輝き、勢い、落ち着き等)である。これは心の動きと直結・連動しているだけに、その変化から相手の心中を察知し、対峙の優位性を築くことに繋げていくものとなる。
最後になるが、師から少年剣士へ訓話の中で、投げかけられた質問の逸話を披露する。
一日の仕事が終わり、心地よい疲れを感じながら帰宅の途について川土手を歩いていた。ふと見ると、そこに可憐な、名もない野の花が2、3輪咲いていた。
〇ある人は、その花には目もくれず、下を向いたまま歩いて行った。
〇ある人は、その花を踏みつぶして、立ち去って行った。
〇ある人は、一瞬目をやりながら「おっ!きれいだなぁ。」とつぶやいた。
〇ある人は、その花を摘み取って持ち帰り、部屋に飾って、眺めることにした。
〇ある人は、花を見た瞬間、同じような田舎の情景を思い出していた。
そういえば田舎の両親にはすっかりご無沙汰しているなあ。連絡してみようかなあ。
帰宅すると早速メールを送ってみた。
さぁ!あなたはどうしますか? (受付日:令和7年5月16日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。