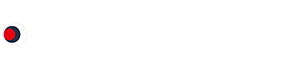図書
『令和版剣道百家箴』
「私と剣道について」

剣道範士 島野 泰山(大阪府)
小学1年生より、父親から初めて竹刀の握り方の指導を受けて、79歳を迎えようとしています。その間、先生方から御指導を受けて多くのことを学ばせていただきました。
今の年代になって、つくづく剣道を続けていて良かったと、実感しております。まさに「継続は力なり」の心境です。
剣道の特性につきましては、諸先生方の著書や『少年少女武道指導書 剣道』(日本武道協議会発行)の中で、詳細に説明、解説されております。
約50年前に大阪城の修道館に於いて、全剣連講師の中野 八十二先生の講話で、「剣道は年令と共に筋力は低下していくが、気力は修錬と共に益々充実していく」とのお話がありましたが、当時は若年でもあり、実感がありませんでした。
34歳の時に、大阪府警察の現役選手を引退し、警察大学校(当時は東京都中野区)の「術科指導者養成科(剣道)」に半年間の入校を命ぜられました。
当時の主任教授は松永範士と岡範士、そして講師の先生方は、剣道界最高峰の中野範士、森島範士、伊保範士、中倉範士でありました。稽古は厳しかったですが、今から思えば、私の剣道人生の中で一番充実した贅沢な半年間でした。
入校中の授業の中で、主任教授である岡範士から、「剣道とは、相手が自分を打ってくる。打ってこようとする瞬間に対する自己創造である」との講話がありました。その瞬間において、自分はどうするのか、迷っている時間はない、瞬時に判断しなければならない、自己創造をしていくとの内容でした。
また、大阪の西範士から、一回の稽古の中で、「会心の技、会心に近い技が一本でも出たら、その日の稽古は良い稽古だった。」とよくお話をされていました。いわゆる「無心」の技でしょうが、良い技を出そう、打とうと意識すればする程出ないし、出せないことと思います。
それは、日頃の正しい剣道、理合にかなった修錬の積み重ねや継続が生み出すものであると思います。
「離見の見」
約600年前、室町時代に「能」を大成した「世阿弥」が、能の奥儀の一つとして「花鏡」で述べた言葉です。
能の演者が相手と対峙しながらも客観的に見ると冷静に状況を判断でき、次の一手が思いつく、と説かれています。「離見の見にて見るところは、見所同じなり。」見所とは能の観客席のこと。」
先人が残してくれた教訓から学び、剣理の向こうにある玄妙さを求めていくことが大切だと思います。日々の稽古の中で客観的な視点(「離見の見」)を持つ人は、何かを自得出来るのではないでしょうか。
「智仁勇」と生産剣道
剣道が復活し、全日本剣道連盟初代会長の木村 篤太郎氏は、「智」という真実の探究、「仁」という人との触れ合い、「勇」という正義と克己心の三徳を標榜されております。
剣道を通じて「道」に遊び、「道」を楽しみながら、生涯剣道を目指したく存じます。(受付日:令和7年6月3日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。