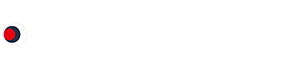図書
『令和版剣道百家箴』
「師のことば(日々稽古)」

剣道範士 上垣 功(奈良県)
高度経済成長から時が進めば、少子化が加速度的に進行する現今の日本、人口は激減時代に入り、同様に剣道人口も減少の一途を歩んでいます。終戦直後に生まれた一人として、剣道の将来、「これからの剣道活性化はどうすればよいのだろうか?」と、考えざるには居られません。
終戦直後のベビーブームで育った私は、生活に何不自由することもなく、言わば飽食の時代に、のんのんと生きてきました。勿論、今は亡き両親のお陰であります。13歳から始めた剣道は、明治末期に若干剣道の経験がある祖父からの手ほどきや、学生時代に柔道を懸命に勤しんでいた父の影響が大きく上げられます。若い時代は血気盛んで傍若無人な振舞い、礼法などとは程遠く、今思えば汗顔の至りです。まさに今日あるのは言うに及ばず、一つ一つ懇切丁寧にご教示頂いた先師方の温かい、そしてきめ細かい中の厳しい「教え」でありました。私にとっては、その道は牛の歩みであり、今はまだ山の中腹であります。
先師からご教示賜った多くの言葉の中で、心得て修錬した内容は次の通りです。
・『袴の裾が波打つようでは本物ではない』
学生時代に剣道部長であり、学長であった先生から、心の錬りを説き諭された。
・『人並みの稽古ではだめだ』
人並みの稽古では人並みだ。そこからの積み重ねの稽古が、自分を創るのである。真の敵は己、不言実行の態度で黙って理屈を言わず、己との闘いを黙々と突き進む修行態度である。
・『不敗の位から水えん刀の位までを楽しめ』*1
相互の稽古の中で、有効打突をとれば有頂天になる。それはまだまだ初心の段階だ。楽しむのは遠間(不敗の位)から触刃の間、そして交刃の間(水えん刀の位)、最後に打突の間までのその道のりを楽しむのだ。これは、永きにわたっての修錬を重ねなければ自得出来ない難題であろう。
・『眼前の睫』
ある書物の中から賜った戒め、「自分が持っている心を磨けばよい。健康な、生き生きとした、綺麗で、塵一つもない心に仕上げなければならない」生涯の課題である。
・『機と溜めの修錬』
遅すぎもせず、早すぎもせず、溜めが丁度いい頃合いのところに来て打突する。
「鹿威しは、水が溜まっていよいよ一杯となり傾き、水を滑らせて戻っては音を響かせる。その戻る機のことである。出来の悪い鹿威しは拍子が抜けて早い。あるいは、何時まで経ってものらりくらりとしてなかなか鳴らぬ鹿威しもある。よくよくその趣きを味わってもらいたい」と、『機と溜め』について、このご教示を実践している。
・『しっかり習え、しっかり稽古せよ、しっかり工夫せよ!』
先師からのこの文言は、耳にたこが出来るほど言われていた。剣人は誰でも熟知している柳生新陰流の教え「習、錬、工」。淀みなく求める姿勢を変えず、剣の習熟度を高めることである。
・『打たれる稽古をせよ』
未熟な時代は何としてでも打ちたい、打たれたくない気持ちがある。身体を屈折したり、防御に徹したり、「これは身を捨てない稽古だよ。身を捨ててこそ生きる道があるのだ」と。
・『素位に行ずる』
今の持っている力量(位)で上を観ず、下をも観ず、百折不撓の修錬を重ねることだ。
・『白鷺の間』
白鷺は、小川で泳いでいる小魚を観つけるや、静かに小魚に足元の間を詰め、嘴で一気に小魚を捕る。先師はこの「間合の詰め」を、「白鷺の間」と名付けたようである。このお話を頂き、剣道の間合の大切さと、その機会を逃すのではないと、肝に銘じた。
・『勝手口から入って来るな』
「あるお家へ訪問した時、あなたは勝手口から入りますか?堂々と玄関からお邪魔しますと、門戸を潜るでしょう。あなたの稽古は、勝手口から入る稽古だよ」と戒められた。三殺法が出来ていなかったのである。
これらは十分ご承知の「教え」と思いますが、これからも稽古を続けてくれる世代の皆様に何か一つ、修錬の糧にして頂ければ幸甚に思います。
物は豊富、消費は美徳、一方では公害問題が大きく取りざたされています。ある高名な僧侶は「物で栄えて、心で滅ぶ」と言われています。今こそ道徳心を高め、精神面の涵養に努めて、剣の理法である「心法、刀法、身法」から、「人間完成」ではなく「人間形成」とした、剣道の終わりのない修錬を歩んでいただきたいと、願うばかりです。そして次代を担う剣士皆様への伝達と撫育が、私にとって、先師への恩返しと思っています。フレイルの時代に置く我が身、さらにこれらの「箴言」を守りながら、邁進していく所存であります。(受付日:令和7年4月15日)
*1 *「水えん刀」の「えん」は、「氵(さんずい)」に「豊(ゆたか)」と「盍(こう)」を組み合わせた字です。
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。