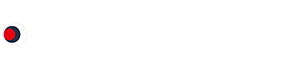図書
『令和版剣道百家箴』
「伝承文化剣道の実践」

剣道範士 千葉 胤道(東京都)
私達が日々修錬している剣道は急速に国際的にも普及、発展している現状があります。国際剣道連盟には64カ国・地域が加盟しておりますが、剣道は我々の祖先によって創造され、日本人の長い歴史と伝統によって独自な発達を遂げてきました。
戦後の剣道史を紐解くと、昭和20年(1945)終戦、その後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の統治下で剣道禁止令により、日本の剣道界は暗黒の時代となりました。昭和26年(1951)、サンフランシスコ講和条約締結、翌年の昭和27年(1952)に、日本は独立国として剣道復活の道が開け、戦後の剣道が歩み始めた時でもあります。
昭和27年5月24日、加盟43団体にて東京都剣道連盟(東剣連)が創立され、同年10月14日に剣道人の念願であった全日本剣道連盟(全剣連)が新たな理念をもって設立されました。
私が剣道を学び始めたのは、昭和29年(1954)4月のことで、東京都文京区小日向台町に所在した「妙義道場」に少年部が発足したと同時に入門しました。当時8歳の小学校3年生でありました。道場館長には教士の長井 武雄先生、道場師範には「昭和の剣聖」持田 盛二範士(後に十段)、増田 貞之輔範士、中野 八十二教士(後に範士九段)の各先生、少年部の指導は山下 惣作教士でありました。名人といわれた60歳代の持田師範から、私達小学生数名が少年指導終了後に、道場のお風呂に入れていただいたことが大きな思い出として残っています。東京都私立城北高等学校剣道部時代は、東京高等師範学校卒業の丸山 鐵男(後に範士八段)先生に、指導理念の「師弟同行、交剣知愛、文武両道」、加えて指導方針であった「正しい心、正しい姿勢、正しい真っ直ぐな剣道」を指導され、明治大学剣道部員時代には、師範の森島 健男(後に範士九段)先生から、稽古の道しるべとして「稽古で初太刀をおろそかにするな、そして、相打ちの勝ちの中に極意がある」「初太刀一本、千本の価値」を常に頭に入れて稽古をすることの大切さを教えられました。「千本の価値」とは無駄打ちをなくすことをいっています。会社勤務をしていたトッパン・ムーア(株)剣道部においては、武道専門学校卒業の中村 伊三郎(後に範士九段)先生よりご教授をいただきました。日本を代表する有名な素晴らしい先生方に指導を受けることができ、私にとっての貴重な財産となっております。
振り返ってみれば早いもので、「妙義道場」少年部に在籍して以来、71年の歳月が過ぎました。当時の思い出が走馬灯のように頭の中で駆け巡っています。昭和29年10月に第1回文京区少年剣道大会が開催され、小学生の部に出場しました。決勝戦審判員の先生方は、他の大会では類をみない、主審に持田範士、副審には増田範士、中野教士でありました。また、昔の関東の稽古は間合いが近く、派閥が強かった。その状況下で持田範士は範士斎村 五郎先生とともに派閥の存在を弱め、間合いの遠い稽古をさせようと尽力された功績は多大であった、と伝えられています。「持田盛二先生遺訓」に「剣道は50歳までは基礎を一所懸命に勉強して、自分のものにしなくてはならない。普通、基礎というと、初心者のうちに修得してしまったと思っているが、これは大変な間違いであって、そのため基礎を頭の中にしまい込んだままの人が非常に多い。私は剣道の基礎を体で覚えるのに50年かかった」と教えています。「妙義道場少年部」では徹底的に基本動作を指導されました。小学校4年生時の昭和29年10月10日(日)、第2回全日本剣道選手権大会が、全国から55名の選手が出場し、メモリアルホール(旧両国国技館)にて開催されました。この選手権大会では、一回戦終了後の少年指導演武に出場し、貴重な体験を得ることができました。二回戦終了後は、女性剣道家の錬士多賀 蓁子先生と錬士高野 初江先生(神奈川県教士八段高野 力先生の祖母)の対戦と剣道対薙刀試合の特別試合、三回戦終了時に、柳生制剛流抜刀、四回戦後に天道流薙刀之形、そして決勝戦前に新陰流兵法正統の勢法が披露されたことを記しておきます。
次に、「持田盛二先生遺訓」第二弾を特記しておきます。
「稽古は先ず技を習熟し 次に気を練り 更に間合いを工夫して 最後は案山子のように ただ立っていればよい」
1.「技を習熟し」とは、体格、性格に合った技を身につける。この技が自身の得意技になる。また、技は教えられてもできなく、自分で創っていかなければならない。
2.「気を練り」とは、技は稽古によって上達するが、気は難しく、座禅によって気を練るしかない。気を練ることは心を練り、呼吸を練ることである。呼吸は数息観により「いーち、にーい、さーん」と、階段を昇る時、電車に乗っていてもできる。従って、心が満ちれば、頭の上から足の下まで気が満ちて隙がなくなる。高段者は「心」について、若い修業者に教えることが必要である。
3.「間合い」は相手との距離。相手に対して気が充実し、自身が整っていて、いつでも打突できる状態を自分の間という。
4.案山子は『猫の妙術』に書かれている年老いた猫のように「気」が充実していることで(体から出ているエネルギーによって)、鼠が近寄れないことをいう。
高段者の先生方が持田先生に稽古をお願いすると、「先生の懐に吸い込まれる」「心で心を打たれた」との話を伺いました。先生には大学2年生までは切り返し・掛り稽古のみの指導でしたが、上級生になって指導稽古をいただいた時に「蹲踞後、構えたら身体が膠着した感じを受け、容易に動けない状態」になったことが心に鮮明に残っています。中段の構えとは「真っすぐ振りかぶり、振り下ろしては、力が入らないところが自分の構え」である。また、「切り返しを受ける時は、竹刀に刃があると思い、刃を保護するよう受けなさい。竹刀剣道から脱却しないことには、真の剣の道は得られない」と教えられました。また、先生の先祖である持田 監物は、剣聖上泉伊勢守 信綱とほぼ同時代の武士であり、同じ城に居ました。信綱は「用心深くして、武芸者として態度は謙虚であった」との人物像があり、先生は憧れと尊敬を抱いていたそうです。持田先生の遺訓をもって錬磨することが、剣道の深さを勉強することに繋がると思料しております。
全剣連が発足した時点での剣道は、戦後の環境下において、体育スポーツとして出発しましたが、昭和50年(1975)に「剣道の理念」が制定され、武道としての「道」になりました。現在の剣道は伝統性と競技性の二面性がありますが、「剣道の本質は真剣勝負」であり、一撃が生死の境ともなります。真剣勝負は一本のみ、二本目はないと思い稽古をする。そのためには日本刀の操法を知る必要があります。竹刀は刀の観念で、木刀は刀の代用と教えています。現在は試合偏重、勝利至上主義による竹刀技術の末節に流れているという説がありますが、剣道の原点は「真剣勝負」です。私達はここで日本の剣道を原点に返って検証するとともに、健全な状況で後世に残していく責任と義務があります。剣道のよき伝統を次の世代、先の時代にバトンを繋げていくことが肝要です。(受付日:令和7年3月28日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。