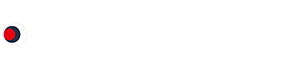図書
『令和版剣道百家箴』
「剣道愛好家に伝えたいこと」

剣道範士 目黒 大作(秋田県)
昭和27年。戦後、剣道がスポーツとして復活。この年、全日本剣道連盟が発足する。期せずして私が剣道を習い始めた年でもある。以来73年間、習い続けて今日に至る。
自身の習いを振り返ると、幼少の頃、基本の習いは強制ではなく、自由にのびのびと楽しむことから始まった。勝負を意識した時期、自らの意志で挑戦し、悩み苦しむことも負担とは思わなかった。教職についてからは、教えること(教育体)と、自らが学ぶこと(修行体)の両立を図る、教育剣道実践者としての厳しい道程の始まりであった。指導者として成果の挙がらない時の挫折感、自らの技量の停滞や怪我、八段の難関にどう立ち向かうかなど、至難の繰り返しなれど、常に物事を前向きに捉え、活動することができた。それは、時々の師の暖かい見守りがあったからだと思っている。
一方、戦前の先達の艱難辛苦の修業を常とする鍛錬の様子を耳にするとき、戦後スポーツとしての剣道にも厳しい修錬の必要性を強く認識するが、それをどう伝えていけばいいか、修錬の在り方について迷う所である。
今日、少子化が進むなかで、伝統文化としての剣道を次世代にどう継承していくのか。また、高齢者の生涯剣道をどう導き、生きがいに繋げていくのか、課題は大きい。だからこそ、今、剣道の不易と流行についての再確認の必要性を感ずるものである。
「多様な価値を求めて」
剣道は、幼少年から高齢者まで、楽しむ人から極める人まで、多種多様な愛好者によって構成されている。また、一人一人の剣道に対する願いも多様である。深浅は別として、これらすべての人に剣道の特性が行き渡ることである。
技術的錬磨、精神的修養、身体的鍛錬など、個人が求めるものは、画一ではない。特に生涯剣道が求められる今、高齢者の心身の健康と、生き甲斐を充足させるものでありたい。あらゆる愛好者が容認できる、ゆとりある剣道の特性こそが必要であり、皆が剣道で満たされることを願うものである。その為にも指導や各層のリーダーが現在の特性をどう具体化していくかが問われることになる。
「習いの継続は極意を受け継ぐ」
中級、上級へと段階的な習いの中で、多くの先生方からの指導を仰ぐ機会が多くなる。師の指摘、助言の一言は、技量向上等に不可欠なのである。しかし、指導の一言は、その人の「受け止める下地」が出来ていないと伝わらない。それは、修錬を重ねて初めて体得できるものである。ある時点で、胸につかえていた師の一言が理解でき、実践できる瞬間がくる。その時の思いは、まさに「至り得れば、事も無し」という一言に尽きるものである。それが稽古による自得である。剣道の技量の向上には、この繰り返しの稽古を重ねることであり、終わりない修錬なのである。どんなに時代が変わろうとも、稽古以外での極意の伝授は考えられない。「継続は力なり」。自らの剣道を高めるには、「継続」することが絶対の条件である。
「自ら求める厳しい錬磨」
過剰で抑圧的な鍛錬が問題視される時代ではある。しかし、古今変わらないのは、自らが決意(自己決定)する厳しい鍛錬への没入は、剣道を極めるための必須条件であり、それは強要されるものではない。そこでは、技量向上のみならず、修養的な価値は、人としての厚み(自己形成)を付けることに繋がるものである。
物事の失敗の繰り返しから物が見えてくる、という体験知こそ、身体への確かな定着を図るものである。昔から剣道が、「打たれて学べ」、「打たれて強くなれ」と言われる所以である。
自由奔放の時代。人間らしく生き抜くためには、自分を厳しくする自己変革が必要であり、それを剣道修錬に求めたいものである。
今求められる修錬の在り方とは、先達の教えを大切にしながらも、世の中の移り変わりを先取りし、適宜対処していくことである。中でも大切なことは、基礎・基本の積み重ねの基盤のもと、競技スポーツとしての剣道と、伝統文化としての剣道の、双方の利点を取り入れながら、その時代に添った指導法の構築が急務と思われる。
前述した「多様な剣道の価値を求めて」「習いの継続は極意を受け継ぐ」「自ら求める厳しい錬磨」といった、根底に流れる伝統文化としての剣道の価値は、時代を越えても、変わらぬものであることを改めて申し述べ、終わりとする。 (受付日:令和7年6月3日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。