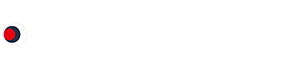図書
『令和版剣道百家箴』
「これからの剣道について」

剣道範士 近 光正(東京都)
はじめに
永い歴史の中で、無数の先人たちが、「挑戦と創造」を繰り返し、剣道の高度な技術、高い精神性を築いてくれました。かけがえのない宝を残して下さったことに心から感謝しつつ、剣道を通じてどこまで社会に貢献していけるか。そのことに「挑戦と創造」を続けていくことが、剣道という一道を歩む者の務めだと私は考えています。
◆現在の剣道における課題
★少子化に伴う剣道人口の確保
一、中学校において剣道が正科に採用されている状況を活用した対応策。
二、小学校において剣道が正科に採用されるよう、文部科学省に積極的に働き掛けを行う。
三、全国の警察署において、地域住民に対する剣道教室を開いて、小学生や中学生だけでなく、一般市民にも剣道への理解と剣道の楽しさを感じてもらい、剣道人口の拡充に努める。
以上三点、ご提案致しましたが、どれもそう簡単ではないかと思います。しかし、剣道人口の確保という意味では、剣道をする場をまず確保しつつ、その上で剣道の楽しさを味わってもらえるように、指導法を含め、工夫を少しづつでも重ねていくことが大事なのではないでしょうか。
剣道に携わる方全員で、少しでもやれることを積み重ねてゆけば、剣道自体は大変魅力的な武道ですので、剣道人口の確保は必ず達成できるものと確信しております。ここでは、紙幅の関係もございますので、二点目について詳しく述べさせて頂きます。
剣道は、日本の伝統的武道の一つであり、日本古来の精神性や考え方が大変凝縮されたものと認識しております。道場を神聖な場所として一礼して稽古場に入ること、裸足で稽古するため稽古場を綺麗にすべく雑巾掛けを行うこと、先生に打たせてもらって技を磨き、正しく指導する先生に感謝の念をもって稽古すること、稽古着をきちんと畳むことで衣類を大切に扱うこと、試合に備えお弁当を作ってもらい、応援にも駆けつけてくれる親に対し、感謝の念を持って接する機会になること等、どれをとっても小学生においては、学ぶべき日本古来の精神性や文化であると思われます。
剣道は身体を鍛え成長を促すだけでなく、そうした我が国の精神性や文化が凝縮されたものであり、その点を踏まえ中学校同様、小学校の正科の一つとしての採用を文部科学省に働きかけて頂ければと思います。そして、小学校の体育館を土・日に解放してもらい、小学校には剣道クラブの開設を呼び掛け、小学生を指導する社会体育指導員を派遣して、指導員の確保を図る仕組みを構築して頂ければと思う次第です。
◆剣道の素晴らしさ
剣道、それは「自分を映す鏡」です。相手と対峙した時、何がしたいのか。勝ちたいのか。そこには自分の心がすべて表われます。「打った、打たれた」は、本来の剣道が求めるところではありません。打つ、打たれるは二の次。「自分と相手の心と心の真剣勝負」です。激しく、強く打ってはいけません。相手の心を打つのですから優しく必要な分だけで表現します。
古人の訓えにある「三無の剣」、すなわち「無理なく」「無駄なく」「無法なし」を求めていきましょう。
剣道を通して自分が成長しながら、周りをよく成長させて、周りを幸せにすると、必ずその幸せが自分に戻ってきます。この生き方こそが、自分を大切にするという真の生き方です。皆さんと一緒に、この日本の良き伝統文化である「剣道」を正しく学び、後世に繋いでいきましょう。
おわりに
◆「と」と「は」の違いの剣道
「あなたと私」「私とあなた」では争いになります。「あなたは私」「私はあなた」の剣道を目指して下さい。二元相対に対して「一元絶対」という言葉がありますが、「絶対」というのは漢文の正しい読み方では、「対を絶する」と返り点をつけて読むのです。要するに、対立を絶する、対立をなくすということです。相手と一つになる。「相手に従うの剣道」を目指して下さい。
失われた20年、30年とも言われていますが、2050年には日本は世界が認める素晴らしい国になると予言された哲学者もおられます。
世界の模範となるような日本を目指して、剣道を通じて少しでも貢献できるよう、皆さんで力を合わせて頑張っていきましょう。(受付日:令和7年5月14日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。