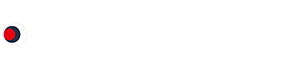図書
『令和版剣道百家箴』
「文武不岐」
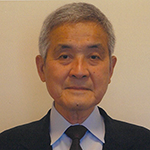
剣道範士 髙山 陽好(茨城県)
私が第8代館長を務めている水戸東武館は、明治7年に創設され令和6年1月に150年を迎えた剣道場である。一町道場がこのように長い歴史を刻んでくることができたのは、館創設者の旧水戸藩士小澤 寅吉が剣道指導の基本精神に文武不岐と定めたこと、多くの道場の先人達がこの精神を愚直に守った剣道活動を継続してきたこと、そしてこれを理解して物心ともに協力、応援をして頂いた方々が常におられたお蔭であると信じている。
この文武不岐は幕末に創設された水戸藩の藩校弘道館に由来する。弘道館は水戸9代藩主 徳川 斉昭が、幕末の停滞した社会、行き詰まった行政を打開して国家の存立を全うするためには真の日本人を育成する必要があるとの自覚に基づき、藤田 東湖、会沢 正志斎などの優れた学者の意見を用いて天保12年(1841)に創設したものである。その教育の精神は、忠孝無二、文武不岐、学業一致(学問・事業一致)の3つである。斉昭は「文武は武士の大道にして人々出精すべきこと」と示唆して文武兼備の人物の育成にとくに力を注いだとされる。
矢倉奉行と弘道館剣術指南役を務めた小澤 寅吉は、この文武不岐を身をもって示す逸材であった。しかし明治維新により幕藩体制と武士階級は消滅、弘道館も1872年(明治5)に閉校となり、人づくりによる国家護持という建学の精神も終焉を迎えたのである。そこで彼は廃れゆく武士道精神、武道の衰退を憂い自邸内に水戸東武館を創設し、剣術の振興と人材の育成を目指すことになった。
創設当初は御一新による廃刀令や兵器の充実、近代化が進み、剣術の修業などは時代遅れで無用の長物との誹謗中傷を受けたと資料にある。しかし彼は門人達に対し「太刀振りて何するものと人問はば御国護れる業と答えよ」の道歌をもって論し、剣術の修業は必ず世の中に役立つ人づくりなるとの自信を持って指導を続けたという。その明察の通り3年後の明治10年西南戦争が勃発、薩摩軍の示現流に近代兵器の官軍が苦戦、時の政府は抜刀隊を編成し対抗、戦いを好転させた事案があり、これを契機に武道修業による心胆の錬成の必要性が見直され、警察、軍隊そして教育に武道が復活したのである。我が意を得たりとした彼の喜びは、いかばかりかと想像するに余りある。その後この道場からは、近代剣道の礎を築いた内藤 高治、門奈 正、佐々木 正宣などの名剣士が生まれて、天下にその名を大いに轟かせたのである。
先の大戦は道場建屋焼失、GHQの剣道禁止命令という大きなダメージをこの道場に下した。この危機に立ち向かったのは、第4代館長の小澤 武である。彼は水戸の篤志家たちに文武不岐の精神に基づく剣道修業による青少年の健全育成の必要性を説いて資金を集め、自邸裏の林から木材を調達するなどして剣道が解禁された昭和28年に現道場を再建し、剣道指導を再開したのである。
彼は剣道指導の際には常に文武不岐を説き、学問と剣道は車の両輪、どちらにも偏らず精進して世の中の役に立つ立派な人間になれと論した。道場再建と同時に入館した私も仲間達と共に耳にタコができるほどこの訓示を聞かされたものである。後にこれを分かり易くするために「勉強します、剣道します、よい行いをします」との標語をつくり子供達に唱和させた。これは現在も稽古終了時の重要な儀式として続いている。
道場再建後70余年、この道場からは剣道九段1名、八段6名の剣士を輩出したほか、官界、財界、教育界、出版界、医学界等に多くの優秀な人材を送り出している。私は文武不岐を具現化し易い警察に身を置いた。剣道特練生を終えた後も稽古を続け、警察業務に必要な法律、実務の知識の習得に励みながら仕事を続けた。長い警察官時代に大きな失敗もなく、県民の安全確保と治安維持に貢献できたのも、文武不岐精神をこの道場で叩きこまれた賜と感謝しているところである。
そして館長を任された今、創設150年の歴史の重みをひしひしと痛感している。この重圧の中で先輩、同僚の協力を得ながらこれまで先人が培ってきた文武不肢の精神を中心に置いた青少年に対する剣道指導を愚直に継承している。また東武館に伝承されている北辰一刀流等の古武道の保存活動、剣道の更なる発展を目的とした全国少年剣道大会、成人剣士による県下剣道大会の開催、外国人インバウンドを主とした武道体験などに尽力しているところである。剣道人口が減少するという逆風の中、この道場をさらに発展させながら次代に引き継いでいく責任は極めて重いものがあるが懸命の努力を続ける覚悟である。
最後に現在剣道を修業中の若い剣士には試合の結果や技量の向上ばかりに偏らず、文武兼備の人物を目指すことを期待したい。文武不岐は決して言い古された精神論ではない。世の中がいかに混迷しようとも学識に基づく正確な判断力と剣道で培った胆力、実行力を備えていれば必ず社会に役に立つ働きができると信じるものである。(受付日:令和7年5月1日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。