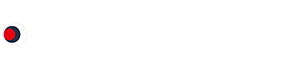図書
『令和版剣道百家箴』
「聞き書き修行録」
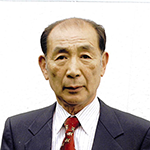
剣道範士 矢作 恵ー郎(山形県)
剣道を始めたのは高校2年からで、先輩から「お前背中が丸いな剣道をやると直るぞ」、と言われたのがきっかけでした。
卒業後、山形県の警察官を受験し、警察学校で1年間の教育訓練の後、交番勤務となり、同時に剣道特別訓練員に指名され以後、13年あまり各種部内外の大会に出場しております。
特別訓練員が解除されてからは、警察学校の剣道教官、その後、警察本部の術科係長として剣道を担当しております。警察学校在任中の半年間、警察大学校の術科指導者養成科の剣道科程に入校しました。
ここでは伊保 清次先生、松永 政美先生、後藤 清光先生が指導教授でした。その他部外講師として、日本剣道形は皇宮警察の中村 伊三郎先生、居合は中倉 清先生、一刀流は松元 貞清先生等、多くの先生方から指導を頂いております。
今でも記憶に残っているのは、「剣道形は喧嘩ごしでやれ、そして一本一呼吸で出来なければせめて二呼吸でやる努力をしなさい。呼吸法の伴わない形は剣道ではなく筅踊りである」と話されたことです。聞き流してしまい未だに身についておりません。
当時講習生の1人でした、兵庫県警の安倍先生だけは顔を赤くし、汗を流して形を稽古されていたのが記憶に残っております。普段から一呼吸での形を打っていたからだと思います。
最近呼吸法が気になり手持ちの資料に目を通しておりますが、具体的に記載されているものを見つけることが出来ずにおります。
毎年全剣連の講習を受講しておりますが、呼吸法について触れられる講師の先生は見当たらない様な気がします。
大分前になりますが、講師の先生に形の呼吸法について質問したことが有りますが、お答えは全剣連で触れてないので答えられないとの答えでした。確かに全剣連発行の資料を調べると長呼気丹田呼吸と言う言葉が有りました。
又、『日本剣道形解説書』の「剣道形の指導上の留意点」の十五に「呼吸は構える時に吸気し、前進するときは丹田に気迫をこめ、呼気の勢いで打突させる。」とありましたが、それ以上の説明は見つけることが出来ませんでした。
最近、堀籠 敬蔵先生の『日本剣道形考』の中で、「構えて息を充分吸い込んで臍からさらに足の裏まで下げ、更にここより息を上げて臍でおさえ、三歩前進機を見て、打太刀は呼気で打った後そのまま息を止めて元の位置に帰る」と有りました。重岡 昇先生も『全解日本剣道形』で、概略同じことを話されております。
平成4年に山形県で国体が開催されました。これに向けて中央講師として岡 憲次郎先生にお願いし、4年間指導を頂きました。
先生が強く指導されたのは、「切り返しは最後の面まで一呼吸でやること」でした。当時は何とかやれるようになりましたが、今は年のせいもあり、とても出来ませんが、出来るだけの努力はしている積もりです。
もう一点は右足を少し出しながら、左足を継がないで面を打つことです、長年の癖で足を継がないと体が前傾する等、容易には身に付きませんでした。
この面は第70回の全日本選手権大会の準決勝、決勝戦で愛媛の村上選手が放った面がこの面であったと思います。
私自身、国体が終わって職場が変わったこともあり、退職までの10年近く剣道から離れた生活を送りました。退職して時間の余裕が出来たことから、剣道を再開しております。
当時、山形県は長年にわたり八段不在県であり、八段受審を強く勧められました。
稽古開始から間もないこともあり、不本意でしたが東京審査を受審しました。結果は二次審査で不合格、翌年も同じことの繰り返しで、再び二次審査で不合格でした。
同じことを繰り返していては一次の合格も難しいと思い、稽古方法を全く変えました。
誰に稽古をお願いしても、最初の2分間は審査の積もりで面の初一本を目指し、これが終われば息の上がる打ち込みに近い稽古方法を1年間続けました。
今までは同じ相手との稽古が中心でしたが、出来るだけ違う相手との稽古を心掛けました。他県の多くの先生方からも多くのアドバイスを頂き、この中で自分で可能なものを選択して、実際に稽古に採り入れてみました。
一時打てなくなったこともありましたが、止めることなく苦しみながら1年間続けた結果、3回目の審査で何とか合格出来ました。
積んでは崩し、積んでは崩しではなく、苦しくても継続したことが良かったのではないかと感じています。
八段講習会で森島 健男先生から、「あれで八段かと言われない様に今まで以上に稽古をし、そして古典を勉強しなさい」と御指導頂きました。(受付日:令和6年7月3日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。