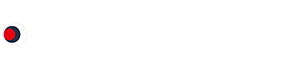図書
『令和版剣道百家箴』
わが師の訓え「課題を求めて!」

剣道範士 渡並 直(愛知県)
戦後GHQによる剣道禁止が解かれた頃の私は、柳の枝を刀に見立てて、近所の子供たちとチャンバラごっこに明け暮れて、ラジオドラマ「赤胴鈴之助」が始まる時刻になると急いで家に帰るのが日課でした。昭和28年(1953)、第1回全日本剣道選手権大会で愛知県の榊原 正先生が優勝しましたが、この方が私にとってかけがえのない師になるとは知る由もありませんでした。私が剣道を始めたのは、昭和32年(1957)、どうしても剣道を習いたくて、当時強豪だった名古屋市立笈瀬中学へ隣の学区から越境入学した時からです。すり足、うさぎ跳び、素振りの毎日でしたが、筋肉と肺活量が大きくなり、疲労で腫れた足や腕がそのまま筋肉に変わっていく実感がありました。
昭和39年にトヨタ自動車に入社しましたが、面接官は後の剣道部長で、白兵戦の経験のある元陸軍将校でした。配属は剣道部先輩の上司がいる機械設計部署でした。当時のトヨタ自動車の稽古は、元立ち10人に対し、掛かり手10人の、休む暇のない掛稽古が中心でした。剣道部師範は近藤 利雄、榊原 正の両先生。水曜日は名古屋刑務所剣道部と合同稽古でした。のちにトヨタ自動車の社長・会長を務め、全日本剣道連盟会長になられた張 富士夫先輩には、体当たりの厳しい稽古はもちろん、仕事でも随分ご指導をいただきました。また刑務官の菅波 一元範士は榊原先生一門の兄弟子という関係になります。
私は名古屋から通勤していたため、稽古が終わると榊原先生を車でご自宅までお送りするようになり、先生の経験など多くのお話が伺えるのは毎回ワクワクする時間でした。選手権者になられても自分は本物になりたいと、時間と費用を使って東京の妙義道場や野間道場へ通われ、大先生からご指導いただいた話などを聞かせてくれました。榊原先生から「剣道を志す者は常に『仁義礼智信』の五常の徳目を忘れてはならない!」「うまいものを食べる余裕ができたら、剣道具や竹刀にお金を使え!」と言われました。「強いだけでは真の剣道ではない!信頼される人になれ!」とも。
「勝ってから打つ、その次は・・・」
稽古でも試合でも、打ち急いで負けることは良くありますが、結局、相手の虚実を見極めないまま「実」に打って出れば、応じや、返しに遭い、負けてしまう。相手より先をかけて打つことを心掛けてきましたが、「相手が怖いから先に打っているのだろう!」と叱られました。攻め勝ってから技を出せば、相手は動けなくなっているから、遅くゆっくりとした技でも打つことができる。榊原 正先生や、楢崎 正彦先生には、こちらが何もできないまま打たれてしまい、その分、敗北感が強く感じられました。
30代半ばの血気盛んな頃、ある研修会に参加させていただき、堀口 清先生と玉利 嘉章先生にお願いしましたが、打って出ようにも剣先が喉元から離れない。無理に出ようとすれば、竹刀がこちらの小手を待っている‼わずかな時間であったがどうにもならず息が上がってしまい、切り返しを受けていただいて、引き退がりました。そのあと某範士も剣先に乗られ攻め返され、壁際まで退がるのを見て、やはり上には上が居るということを実感しました。これこそ堀口 清先生の「その次は打たなくともよい‼」という訓えだと強く感じました。
「竹刀について」
竹刀は剣道の稽古をするのに最も大切な道具で、先革の重さが1グラム変わっただけでも調子が変わります。昔の侍は刀を大切にしていました。我々剣道愛好家は、竹刀を刀のように大切に扱うべきで、高価なものに限らず、良いものを選ぶように教えられました。榊原先生は「お相手の面を打たせていただくのに、節くれだった竹では失礼であるから」と、ご自分で節の部分を面取りされていました。「竹刀作りの名人」といわれた玉利 嘉章先生の竹刀を今も大切に保管しているが、きれいに面取りされていて、実に美しい竹刀です。
現在まで稽古を続けることができたのは、常に課題を与えてくれた良い師に巡り合えたことと、健康に恵まれ、かつ環境を与えてくれた多くの人たちのお蔭と感謝している。目指す目標との乖離を「課題」と見定め、これを克服する努力が必要であると思います。
今年傘寿を迎えたが、「辿り来ていまだ山麓」の心境で、「露の位」の打突とさらなる高みを求めて生涯剣道を目指し、努力を続けていきたい!(受付日:令和7年5月21日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。