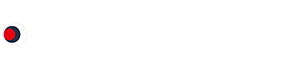図書
『令和版剣道百家箴』
「修行過程における剣の道・研の道」

剣道範士 林 邦夫(愛知県)
はじめに私が剣道家として追求してきた「剣の道」を、つぎに大学教員として続けてきた「研の道」について述べてみたいと思います。
剣の道
中学生の頃は柔道部でした。剣道部顧問の坪井 市次郎先生が郡大会でBチーム1名不足するから試合に出場してくれないか、と言われ剣道を始めました。郡大会の個人戦「段外の部」で優勝し、それを見ていた浅川 春男先生(第4回全日本選手権者・範士八段)にスカウトされ、本格的に剣道を行うようになりました。
高校では、浅川 春男先生に基本稽古を徹底的に鍛えられ、「冴えた打ち」、「打ち切った打ち」を学びました。先生は技術指導をされるとき、「面打ちは、こうだ」、「小手打ちは、こうだ。」、「突きは、こうだ」と言われ、必ず面をつけて模範を示されました。特に、小手打ちは「パクッ」と音がした。また、突きは「気持ちの良い」突きでした。それは「突き放し」になるのでなく「突いて止まる」技術であったことから、危険性が無かったのです。
中京大学では、三橋 秀三先生に理論に基づいた打突動作を学びました。三橋先生は、例えば「中心を攻めて剣先を下げれば、相手が面にくるところを『読んで』、反射的に『面返し胴』を打てば良い。僕のこの胴は、高野 佐三郎先生から学んだ技だ」と言われました。三橋先生は稽古でこの技を何回も繰り返して稽古されていた。まさに、合理的で、洗練された技でした。
近藤 利雄先生は地稽古において前にドンドン攻めて打ってくる稽古で、私は自然に退がりながらの打突になり、最後は懸り稽古になりました。この事により、追い詰められた苦しい中で技を発現し、無理・無駄のない「技」を身につけたのです。
伊保 清次先生は、「サアーコイ」の構えから、竹刀を押さえ面と小手を使い分けられ、また小手から面の二段打ちや担ぎ面、さらに片手右面や片手突きを発現され、技が多彩であったことから、先に技を出す「懸りの稽古」を実践しました。
恵土 孝吉先生の稽古は、試合を中心とした三本勝負の地稽古で息の上がる稽古でした。この稽古により、動きの中で打突の好機を捉えることと、呼吸循環機能を高める稽古ができたのです。
以上のように、剣風・体型の違う恩師たちのおかげで、私はより多くのことを学びました。つまり、先生方に稽古をお願いする気持ちから「先」を掛けて懸の稽古が、(私自身)合理的な技術を身につけることにつながったと思われます。しかし、この原稿を書き終えたとき、鹿屋体育大学の谷口 安則先生から質問されたことを思い出しました。それは名古屋の八段選抜戦の後、「林君、君は誰に指導を受けていますか」と聞かれました。谷口先生は、上述の先生方の指導を受けていることはご存知でした。にも関わらずお聞きになったのは、全先生と剣風が違うからでした。「私は、自分流です。」とお答えしたのを思い出しました。
振り返りますと、恩師から学んだ経験を科学し、学生たちへわかりやすく伝えるという使命感が強くあり、「自分流」になったのではないかと思います。
そしていま、年齢を重ね80歳が過ぎ去り超高齢者になってから分かるのは、経験と研究の積み重ねにより、指導法・コーチングが変わってゆくという事であります。
私は年代別指標を掲げ、稽古に取り組んできました。20歳代から30歳代まで「攻撃剣道」で強くなる事と試合に勝つことを目標に据え、稽古に取り組んでいました。高校時代は、基本に準拠した剣道。大学時代は、強くなることを前提に試合で勝つ剣道でした。教員になってからも学生時代と同様に「勝つ」ことが前提条件で、理論的に納得できる剣道を心掛け、「攻め」と「先」を取る技法を考え「攻防一致の剣道」でした。
40歳代は、48歳で八段審査に受審できることから、「理合剣道」を目指しました。そのために真剣勝負の世界で構築された柳生新陰流の「活人剣」と「殺人刀」の技法と心法を学び、「懸待一致の剣道」を心掛け、理合剣道に活かすことと共に、体力の低下を補うためトレーニングとストレッチ運動を実践しました。
八段を取得してからの50歳代は、「位剣道」を実践し、八段者として「位負け」しない「心気力一致」を心掛け、間合と姿勢を意識しました。つまり、正しい姿勢、正しい呼吸、適切な間合、そして正しい意識をもって稽古に取り組んだのです。
60歳代は、体力の低下が著しくスピード・筋力・パワーが落ちたことを自覚し、それを克服するために「攻応一致の剣道」を構築しました。「攻応一致の剣道」とは、柳生新陰流の「懸待一致」の技法から自ら考え・工夫した懸り、迎える「懸迎一致」の技法です。それを修練する過程の中で、「頸部切り返し」と「切り返しの切り返し」を考案しました。
70歳代は、定年退職後、稽古量が少なくなる一方で時間的に余裕ができました。そのため、これまで培ってきた自ら歩んだ剣道を見直したところ、攻め合い稽古の必要性を感じました。これを克服するため、自身に「気」を入れることで、相手も「気」が入り、「合気」になり、良い稽古、良い剣道を求めたことで確立したのが「相応一致の剣道」でした。
80歳代は、現在進行中ですが、相手と向き合い「対立の関係」の中で真っ向勝負する剣道を考究することで、理想的で美しく美的感覚を求める剣道への進化をもとめることで、「和心一致」の剣道へと導かれるでありましょう。
研の道 ①剣道の原理(五つの柱)
剣道は、身体運動学的には対人競技で打突運動に分類できます。私は「剣道の原理」を下記のように五つの柱に分類しました。
〔身体運動〕⇨〔稽古〕⇨〔有効打突・心身調和〕⇨〔創造・共創〕⇨〔道の文化〕
剣道の身体運動は稽古と言われます。稽古は有効打突を得るために行い、有効打突は心身調和することです。心身調和するためには、相手と共に良い心境を創らなければなりません。これを共に創ることから「共創」と名づけました。共創することにより創造性が高まり、それを何年も続けることが道の文化となり、人間の生命力を高める根幹をなします。
研の道 ②剣道の技術構造
剣道の技術構造を明らかにするために、下記のように技術面(身)と精神面(心)に分けて考究しました。
技術面 身 ⇨〔構え〕 ⇨〔攻め〕 ⇨〔打突〕 ⇨〔残心〕⇨有効打突
精神面 心 ⇨〔予測・読み〕⇨〔判断・決断〕⇨〔行動・実行〕⇨〔備え〕⇨有効打突
技術面(身)は、相対動作の中でお互いに構え、相手を攻め・崩し、隙の生じたところを一拍子・一挙動で打突し残心をとります。また、相手の打突に対して応じて打突することにより、有効な打突を得ることになります。
一方、精神面(心)では、相対関係の攻防の中で相手を予測・読み(察知)、瞬間的に判断・決断して行動・実行すると同時に、常に次に繋がる心構え・身構えを創出します。
こうした両者の戦いの場を心身両面から見ると、構えの中では常に「心気力一致」の心境を創り出し、充実した気迫と気力で「気剣体一致」した捨て身の打突をすることができます。これが剣道の真髄であり、無限大のエネルギーを養うことになるのです。
この技術構造を作成したことにより、各論として構えは如何にすべきか、攻めはどのようにすべきか、打突はどのようにすべきか、残心は何故必要なのか等の原理・原則を解いたのです。
上述の「剣道の原理」と「剣道の技術構造」は、全剣連の中堅剣士指導者講習会(奈良・柳生)で副会長の森島 健男先生が朝食をいただいているとき、突然「林君、一時間目、講話をしなさい。」と言われ、何を話すべきか考えた結果、図式を黒板に書いて講話したのが「剣道の原理」と「技術構造」でした。大学生に講義するときの研究資料が役立ったことを思い出しました。
私は、剣道人生において「剣の道」「人の道」「研の道」を心掛けてきました。「剣の道」は、強くなりたい、試合に勝ちたいことから基本稽古と応用稽古を心掛け、「人の道」は、剣道行政に携わったことから人間形成と人間不形成論を学び、さらに「研の道」は、教員として教育的立場から経験科学と実験科学を融合した研究を試みました。
人は欲があるからこそ進歩・発展します。しかし、その欲が間違うと人間不形成が生じます。従って、先人たちは「正しい」という言葉で指導法の是正を訴えたのが「剣の道」だと思われます。
現代社会は、混沌として先行き見通しがつきません。このような世の中である時こそ、剣道文化(武士道・武道)が効力を発揮します。それは江戸時代に柳生新陰流が「活人剣」を構築し、平和を願った武士社会にあった文化です。
今こそ、若い世代の人たちが「剣道文化」を世界に発信して頂きたい。それは「平和」です。また、さらなる少子化時代になるならば、「剣道文化」を実践できる、若い世代の次の世代のエリート剣士を育成することが使命でしょう。
そのためには、他のスポーツには見られない「残心」の意味づけ、「初太刀一本」「一挙動」という指導用語の吟味、国際普及の在り方の研究、高い技術を将来に伝承するためにも九段位の必要性なども検討していただきたいと思います。最近は、ジェンダーに関する問題やセクハラ、パワハラなどが指摘されています。また、組織づくりや運営方法を他スポーツ団体から学ぶことも必要でしょう。(受付日:令和7年5月22日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。