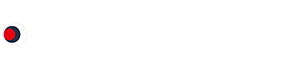図書
『令和版剣道百家箴』
「教育剣道を受け継ぐもの」

剣道範士 佐藤 成明(茨城県)
自分史(概略)
私の幼少年期の世相は剣道界を含めて太平洋戦争を挿んだ戦前・戦中・戦後の激動の時代で、昭和20年(1945)8月15日小学校1年生の夏、終戦の詔勅を疎開先のラジオの前で畏まって拝聴したことを記憶しています。戦後の剣道禁止の時代、多くの人々は剣道の本当のよさを知っていながらも意識的にそれを忘れ去ろうとしていた時代でもあったようです。このような時代に剣道の再生・復活を願う先達が、撓競技の創出をはじめ、涙ぐましい努力をされていたことなどは後年になって知ることです。剣道は昭和27年(1952)4月の日本独立までの約7年の長きにわたって禁止されていました。この期間が私の小学1年生から中学2年生の期間でした。因みに弓道は昭和23(1948)年、柔道は昭和24(1949)年に解禁になっています。
私が正式に剣道を始めたのは栃木県立宇都宮高等学校1年次の後半(1954年11月)からでした。小学校入学前に戦地から奇跡の生還を果たした父(金作)から子供用の木刀を用いての、基本的な動作を「剣道ゴッコ」のような形で教わったこと、撓競技の格技教材採用前の指導法としての教材研究の実験財として基本的な手ほどきを受けてはいましたが、初めて剣道具を着装して竹刀を持って打込みをしたのはこの時が初めてでした。力任せの打込みに先生方は褒めて下さいました。高校2年時に伝統の母校剣道部の再興が認められ、3年次には僅か10名足らずの部員ながら僥倖にも県大会で優勝して関東大会、第3回全国高校剣道大会に出場の機会を得ました。
教育剣道の継承を夢見て
剣道を特技とする体育教師・研究者になることを志して東京教育大学体育学部体育学科に入学し、戦後に結成された部員数20名足らずの剣道部に所属しました。当然、全日本学生剣道優勝大会の優勝を目指し、実力の向上を期して日々の稽古に取り組みました。中野 八十二、橋本 明雄、清野 武治先生の指導陣をはじめ佐藤 卯吉、森田 文十郎、小沢 丘、鈴木 幾雄、村上 貞次、渡辺 敏雄、湯野 正憲先生、その他多くの東京高師卒の先生方からさまざまな御指導や御助言をいただきました。
東京教育大学は、戦後の教育改革により、戦前の東京高等師範学校、東京文理科大学、東京農業教育専門学校、東京体育専門学校が合併して設立された文学部、理学部、教育学部、農学部、体育学部からなる新制大学で、戦後の学校制度の改革では教員養成大学ではないとされていましたが、体育学部は体育やスポーツの学術的研究を推進するとともに、学校体育の指導者養成に高師以来の歴史と伝統を受け継ぐ学部として輝いていました。
道場に来られた先生方は異口同音に「戦後の教育制度の改革で教員養成大学ではないとされているが、教育の本山としての歴史と伝統を有する本学で学ぶ諸君は、将来、剣道の指導者、特に高野 佐三郎先生の『理合の剣道』の意を体した『教育剣道』の担い手にならなければいけない。それが責務である」とか「勝負があるからには勝利に向って邁進せねばならぬが、こせこせとした勝負本意の小さな剣道をやってどうするか!」「高野先生の『理合の剣道、正しい剣道、美しい剣道』を修行せよ!」などと事ある毎に諭されました。中野先生の技の分析的説明をはじめ、先生方の御指導は常に「理・理合」を強調され、「理合の剣道」を念頭に置いたもので、日々の稽古を通してのヒントを与えて下さる指導でした。私たちは先生方の姿を注視し、それを学び取ろう、真似しようと努力しました。引用される言葉は『五輪書』、『孫子』、『天狗芸術論』、『不動智神妙録』、『役者論語』、『運動科学』などからのものが多くありました。教えられた高野先生の「理合の剣道」「教育剣道」の伝統に誇りを持ち、如何に学び受け継ぐかが、私共学生の共通の課題であり、日常の論議の対象でもありました。お手本は、広く高野先生に直接教えを受け、全国で剣道を通じて人間教育に携わっている諸先生方の剣風であり、指導法であり、剣道への取り組み方にありました。私たち全てが立派な指導者になろうとの願いをもって、日々の稽古に取り組んでいました。
学部卒業後、縁あって戦後の東京の剣道史に重要な位置を占める町道場の一つである「妙義道場」の管理人宅に下宿し、持田 盛二先生を中心に当時の日本剣道界の重鎮の先生方が参加する朝稽古で多くの著名な先生方のお姿を拝見し、御指導もいただきました。諸般の事情で道場が閉鎖された後の朝稽古は、講談社野間道場に引き継がれ通うことになりました。
教育実習の指導教官をはじめ在学中に御指導をいただいたそれぞれの先生方から、教師、指導者、研究者としての心構え・使命は「愛を持って事に当り時代を指示せよ、文教新に時代を指示せよ」、「東の精神、西の科学、生采離々たり 斉しく取るべし」「培え育てよ 理想に生きつつ 与えよ総てを没せよ己れを」と歌われた東京高師時代の校歌に示された文言で、先生方の日常の教室内外での生活の中で身を以って無言の裡に数々の御教示をいただきました。修士課程修了後、駒澤大学文学部、東京教育大学体育学部で指導者の一員となりました。特に体育学部に武道学科の設置があって、新たな修行の生活が始まりました。剣道の専門的な指導者を志す武道学科の学生諸君相手の生活の中で、特別に許されて防衛大学校剣道部でのお手伝いと日本武道館に開設された武道学園講師の経験は、私にとって貴重な修行の場を与えてくれたと感謝しています。
昭和48年(1974)10月に新構想大学として開学し、翌昭和49年4月に第一期生を迎えた筑波大学に配置換えとして教官第一号として赴任しました。昭和52年(1977)の東京教育大学閉学までは兼務でした。全剣連の国際委員として剣道の国際的な普及に関わったこと、合せて英文『Fundamental Kendo』(中野先生との共著)、『Nippon Kendo Kata』等の執筆、映画『Door to Kendo』(全日本剣道連盟編)、『テレビスポーツ教室「剣道」』(NHK)に長年携わった事も「理合の剣道」の再確認の意味において貴重で重要な修行の一環となりました。
師の教え
「これからの剣道界は実技と共に現代の諸科学の研究成果の裏付けが必要不可欠になってくるから、多くの研究領域で大いに剣道を研究して、今後の発展に寄与しなければならない」との中野先生の方針に従って、私共はそれぞれ関心のある研究領域の研究室に所属することになり、私は体育心理学研究室に所属、専攻科では格技運動学、大学院修士課程(教育学部)では教育心理学を専攻しました。諸科学の研究成果の裏付けによる「武道学」構築に対する中野先生の意欲を示すお言葉であったと思われます。
修業時代に心掛けたこと
学生時代は当然のこと、指導者の立場となっても、学内外の諸会議や学会等に関わる場合を除き、可能な限り道場に立つことを実践してきました。生来の不器用者の自覚の下、努めて技の基本的な仕組みの理解を通して技の理合を知り、その体得を目指して日常は学生諸君を相手に数多くの稽古に取り組む努力を致しました。出稽古その他、機会のある毎にさまざまな人々とお手合わせをお願いすることを常としました。
稽古以外の時間の有効利用は、読書と授業等の準備に充てることを特に重視しました。経済的に可能な限り教育、体育、心理学、武道関連の図書の収集に努めました。
生来の健康体を過信せず、健康管理や安全管理には充分注意を払った積もりですが、右上肢肘関節の故障による外科手術と、稽古中に横から激突された左膝半月板の損傷は悔まれることでした。
私の信条、座右の銘
幼い時に信者でもない母から贈られたキリストの「汝等、善き行いを以てその身の飾りとせよ」の金言が、私の人格形成に大きな影響を与えてくれました。母の言う「善き行い」とは、「人として成さねばならぬ正しい行い」であって、人に見せるための取り繕った善行ではない。人が見ていようとなかろうと、「してはならないことはしてはならない」というもので、「大學」にある「愼獨」(人のいないところでも身を慎むこと)や論語の「和而不同」(人とし仲良くするのが、いたずらに同調しない)の意に通ずる教えです。こと私の剣道修行は初歩的な段階から教えられた基本、長じて理解できた「理に適った剣の理法」を「善き行い」と捉えて、その道から外れぬようにと、頑なに守り実践することを信条としてきました。
読書のすすめ
専攻科、大学院での武道学以外のテキストは殆ど英文、独文でした。剣道(武道)関連の古文書等の解読も、辞書を頼りに時間をかけての予習、復習でした。数的処理の数学を含めて、高校時代の味気ないと言われる受験勉強、即ち、基礎・基本を積み重ねた学習経験がこの時に有効に作用したものと思っています。剣道における基礎・基本の大切さと同様に「事理一致」「文武不岐」「文武一徳」の教えのための読書、歴史を紐解き、これからの剣道の在り方を考える上での思索の手掛かりとする読書と学習は、更なる剣技の上達に資するものと確信します。
おわりに
「教育剣道」の推進には優れた指導者の存在は不可欠の条件であることは確かです。私は申すまでもなく非力であり、その任には不適切な者であったと自覚していますが、東京高等師範学校から連綿として受け継がれた歴史と伝統の「教育剣道」の理想を求め継承するための仲立ちとなるべく優れた先生方、先輩、後輩の皆様の御支援を得、学生諸君と共に「理に適った、強く、美しい」剣道、すなわち「教育剣道」の獲得、伝承の為に微力ながらも努力してきた積もりです。その成果はこれからの後進の手によって更なる発展がもたらされるものと期待し確信しております。(受付日:令和6年8月28日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。