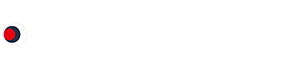図書
『令和版剣道百家箴』
「師の教え」

剣道範士 伊藤 雄三郎(京都府)
はじめに
昭和30年、高校2年から始めた剣道も、それから、かれこれ70年が経とうとしている。
その間、先生方や先輩方に多くの教えを受けた。その一端を述べて、剣の道を求めておられる諸志の何らかのお役に立てればと思う。昭和32年10月、京都府警察宮を拝命。同35年10月、機動隊剣道小隊に配属された。当時、宮崎 茂三部先生は退職された直後であったが、武道師範室には、大森 小四郎・田中 知一・黒住 龍四郎・小川 政之・杉江 憲の各先生方が在籍された。この先生方の一言一言が、私の剣道人生の支えになった事は言うまでもない。
先生方の一言
宮崎先生ー初太刀一本こそー
「私は、あなたの掛り稽古を受けるために来たのではないよ。」と初めて稽古をお願いした時に言われた。人間一度死んだらおしまいだ。だから、剣道をする以上、年齢・段位・先輩・後輩に関係なく、初太刀一本は絶対に取る、という気慨が大切。「一期一会」という言葉があるが、これと相通じるものがある。
大森先生ー面こそ大切ー
練習試合の結果を見ながら、面の取得数が多いと評価された。技の種類は色々あるが、遠くにあり打ちにくい面を、攻めて、乗っていくという気が大切。そうすれば自ら小手も胴も打てるようになる。
田中先生ー間髪を入れずー
名前を呼ばれたら「ハイ」とすぐ返事をする。それが大事。呼ばれて、なにか叱られるのかナ、あのことがバレたのかナと、しばらく考えて返事をする、ではない。手を叩くと「ポン」と音が出る。音が出るまでに間に何も無い、これが大切だ。
黒住先生ーだまし、ごまかしが無いー
だましたり、ごまかして打って、当ったらのを可とするのではなく、正々堂々と攻め合いをし、心と心の争いをしながら、ここぞ、という時に捨て切る。これが剣道だ。ごまかして、だまして打って、当ったと喜ぶようでは駄目だ。
小川先生ー捨ててこそー
「瀬々に流れる栃殻も身を捨てこそ浮ぶ瀬もあれ」の剣歌を引用して、捨ることの大切さを説かれた。こわい、どうしようと迷っていたのでは、実を結ぶことはできない。おそれずに、迷わずに実(身)を捨てるからこそ、岸ににたどりついて芽を出し、実を結ぶことが出来るのだ。
杉江先生ー体で憶えるー
全てが終ってくたくたになった体に「5人1組相掛り」は、きつく厳しいものだった。相手との攻め合いの中で、ああしよう、こうしようと考えるのではなく、自然に技が出る、瞬時に体が反応するようになるためには、自分で限界を設けずに、負荷をかけることが大切。
終りに
勝ったり、負けたりではあったが、多くの試合を経験してきた。が通じて、「逃げない。」「迷わない。」「ごまかさない。」「ひるまない。」という気持で戦ってこれたように思う。日常生活においては、「人との縁を大切にする。」「我以外全て師」という心で生きて来たつもりである。締めくくりとして、尊敬すべき先輩であった、故奥島範士が常に口にしていた言葉を述べて終りとしたい。
・剣先は相手との対話だ。
・剣先の争いの中で耐える肝があるか無いか。
・ここと思ったら捨切る覚悟があるか無いか。
・集中力とその持続。
・打って勝つより勝って打て、の名言を忘れるな(受付日:令和6年8月1日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。