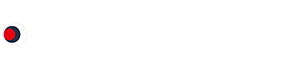図書
『令和版剣道百家箴』
「刃筋と鎬を常に意識し、刀の観念を遵守する」
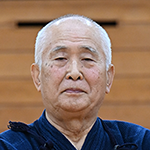
剣道範士 矢野 博志(東京都)
初代剣道部長大野 操一郎先生
昭和34年(1956)4月、静岡県立相良高校を卒業したわたしは、国士舘大学に入学しました。卒業後、助手として大学に残り、平成23年(2011)3月に定年退職するまで、半世紀以上、国士舘大学に育てていただきました。国士舘大学で学んだことを主として原稿を進めさせていただきたいと思います。
大野 操一郎先生は、国士舘大学剣道部の初代部長であり、大学創立者と共に私を国士舘大学剣道部へと導いて下さった恩師です。先生は明治34年2月、島根県松江市に近い玉造村に生まれ、松江中学校で芦田 長一先生に剣道の手ほどきを受けました。大正11年4月、東京高等師範学校体操科丙(剣道専攻)に入学、高野 佐三郎先生らの教えを受けました。戦前は八代中学校、巣鴨中学校で教員をつとめ、戦後、昭和31年に国士舘大学に赴任し、3千人を超える教え子を卒業させました。
私の入学は昭和34年、大野先生が在職4年目にあたり、剣道部も本格的活動期に入り、この年には第5回関東学生剣道新人戦大会での初優勝を果たし、大学・指導陣・部員全員が一丸となり全国優勝への夢を抱き稽古にも一段と気合の入った時期でした。先生はいつも愛用の自転車で大学に通われ、途中の大変急な坂道も一気に漕ぎ切る脚力の持ち主で、しかもそれは晩年まで続けておられました。
入学当時の国士舘大学の道場は、間口27間から30間、奥行き7間程の長方形の建物の中央正面部に50センチ程せり上がった10帖程の畳の部分があり、その奥に大きな姿見、向って左側に太鼓が置かれておりました。細長い道場は、上座中央部に大野先生・斎村先生を中心に左右に先生方が分かれて着座され、対面する形で前列に4年生から2年生、後列に1年生が並ぶ集合体制をとっておりました。
稽古時は上級生の元立ち一列の前に数名ずつ並ぶ形態で、大野先生の太鼓に合わせ、切り返し・打ち込み・掛かり稽古が行われ、地稽古になると先生が元立を交代され、併せて1時間程の稽古時間でした。午後の稽古も同様に切り返し・打ち込み(技の指導あり)・掛かり稽古・地稽古とほぼ2時間の稽古時間でした。試合1ヶ月前頃から試合練習も取り入れられ、これは午後の稽古時間帯か稽古後の時間帯で行われ、稽古後の試合練習時には、終るとくたくたになったものです。
松江中学校時代、大野先生があの内藤 高治先生に稽古をお願いしたときの話です。内藤先生は明治32年、大日本武徳会剣術教授となり、武術教員養成所の教授をつとめ持田 盛二先生らを育てた方であり、大日本帝国剣道形、いまの日本剣道形制定の主査をつとめた先生です。
大野先生は無我夢中に内藤先生に懸かり、何本も面を打ったそうですがいつまでたっても内藤先生は「まだまだ」と繰り返しました。そして疲れてへとへとになったところで、遠間から大きく振りかぶって面を打ちました。すると内藤先生は「よし、まいった」と言い、稽古を終えられたそうです。
「技は遠い間合から大きく打ち込むことが基本。小さい技はだめ」と大野先生は、子供ながらに実感したそうですが、内藤先生の「よし、まいった」の一言が指導の根幹になっているとおっしゃっていました。
国士舘では現在も打ち込み、切り返しを欠かすことはありません。これは大野先生の指導方針の踏襲です。
「高校生、中学生は試合に勝つことばかりを求め、小さく打つことに執着しているが、それでは大成しない。大きな技を身につけさせれば、自然に小さな技は打つことができる。それが剣道だ」と、師範室であの大きな声で強調されていたことを昨日のことのように思い出します。
現在、基本稽古で学生を指導するとき、一般の方を指導するときに必ず伝えているのは遠い間合で構えることです。「構えが正しくなければ正しい技はだせない」ということがわたしの持論です。自分自身が描く最高の構えを執ることを強調しています。蹲踞から立ち上がったとき、そう伝えると背筋が伸び、とてもよい構えになります。
基本の面打ちではこの構えから一歩間合を詰め、正しい構えから大きく振りかぶって面を打ちます。遠間から打ち間に入ったところで竹刀を振りかぶり、肩・肘・手首を十分に使って打ちます。
触刃の間合・交刃の間合・打ち間
間合とは、自分と相手との距離ですが、間合は剣道の生命線だと考えています。間合を覚えるということは難しいことですし、技量や体力によって間合は違ってきます。間合には距離的な要素と時間的な要素があり、それを「間合と間」に分けて教えることもあります。間合は相手との関係で生じるものですから、自分の間合を知ることがいちばん重要です。自分の間合を理解している人は強いし、試合も巧みです。自分の間合を知っているので「ここまでは入れば打てる。ここまでは打たれない」など状況判断にもたけ、我慢ができます。それが溜めとなり、相手に圧力をかけることができます。
国士舘専門学校剣道講師、戦後は警視庁剣道指導室主席師範となった小川 忠太郎先生から「矢野君、竹刀を触れるところが触刃の間、そこから少し詰まったところが交刃の間、さらに詰まったところが打ち間、これを小さな間合という。触刃の間から交刃の間まで入るときに気力を満々にして打ち間に入る。打ち間は打つ間合だけど、入っても我慢することもあるし、打つこともある。ここを勉強すること」と、ご指導をいただいたことがあります。
以来、交刃の間に入るまでに気力を充実させ、打ち間に入ったときには勝った状態を作っておくことを心がけるようになりました。剣道は「打って勝つな、勝って打て」と教えていますが、打ち間で剣先の攻防をしていては、互いによい技を出すことはできません。
間合について、とくに印象に残っているのは斎村 五郎先生の教えです。昭和34年、国士舘大学に入学して間もなく、わたしは恩師高井 利雄先生の手紙と土産を携え、斎村 五郎先生のご自宅にご挨拶にうかがったことがありました。
斎村先生は当時、範士十段、剣道部の師範を務めておられました。その大家に、18歳の学生が訪ねたのですから緊張の連続でした。
「静岡県出身で高井 利雄先生の教え子の矢野 博志です。国士舘大学に入学することができましたので、ご挨拶にうかがいました」と緊張しながら、挨拶したのを昨日のことのように覚えています。
斎村先生は和服姿で静かにお茶を口にされるだけで、無言のままでした。正座を続けるわたしの前に2度目のお茶が運ばれ、ついに3度目のお茶が運ばれたときに、この状態を見かねた奥様が助け舟を出してくださいました。
「お父さん、なにか話してあげたら」
その瞬間、斎村先生は、「質問がなければ、話すことはないよ」と一言でした。
私は1週間後に出直し、質問をさせていただきました。間合についてお聞きしたのですが、「間合は気力だよ」との返答をいただくことができました。
間合は気力……。いったいどういう意味なのでしょう。日記帳にメモを残しましたが、その真意などわかるはずもありません。卒業後、改めてのそのメモをゆっくりと見直す機会がありました。気力とはどのように鍛えたらよいのか疑問に思ったのですが、結局は稽古しかありません。まず自分が大きな声を出す。学生を指導するときは気力を引き出す。それを基本として指導を続けてきました。自分が大きな声を出すことで気力が充実し、相手が威圧できるようになることがおぼろげながら自覚できるようになりました。気力が充実していると、自分の間合で剣道ができやすくなるのです。もちろん相手がいることですので、常に優位な状態が保てるということではありませんが、間合は単なる距離ではないのです。
刀法は刃筋を正すことから始まる
剣道は真剣勝負からはじまり、形稽古、竹刀稽古に変化してきました。時代の変遷とともに剣道も変化してきていますが、真剣勝負を原点とし、刀法に則った剣道でなければなりません。木材を使ったのが木刀、竹材を使ったのが竹刀ですが、すべて「刀」の一文字が入っています。「刀」である以上は、刀法を意識した剣道を身につけなければなりません。
刀法の特徴がいちばんあらわれているのは応じ技です。応じ技は刀法を駆使しなければできません。具体的には竹刀の鎬を使うことです。鎬とは刀の棟と刃の境界をなす線のことです。鎬は刃部よりも厚みがあり、その厚みがあるからこそ、切り込んできた相手の刀に対して応じて切り返すことができます。
竹刀に刃がないことから刀と別物と考えてしまっては、鎬の意識が生まれようもありません。また刃の意識はあっても、鎬の意識が抜け落ちてしまう場合もよくあります。子供や初心者に教えるときは竹刀の弦があるほうが峰、その反対側が刃ということを教えますが、さらに一歩踏み込んで、鎬の説明も加えてほしいと思います。実際に刀や木刀を用いて説明をすれば理解しやすいと思います。最近は木刀による剣道基本技稽古法が浸透してきているので、「刃筋」「鎬」といった事項が低段者にも理解されるようになりました。
刀法に則った剣道を心がければ無理な竹刀操作は減ってくるはずです。「打ってやろう。当ててやろう」という気持ちが強くなると、無理な竹刀操作になりやすくなります。
「刀の観念」を得るための一番簡単な方法は、一度真剣を手にしてみることです。刃筋や鎬と説明しても、真剣を見たことも握ったこともなければその理解も充分なものにはなりません。真剣を手にすることができればたちどころに刃筋、鎬を意識できるはずです。
「剣道試合・審判規則」に、刃筋は有効打突の条件のひとつとして明記されています。刃筋というものは、ただ刃が下を向いていればよいというものではありません。姿勢、構え、手の内などの要素が合わさって刃筋が立った打突が成立します。これは竹刀だけを持っていては、なかなか気づくことのできない感覚だと思います。
刀の観念を大切にし、刃筋を意識した剣道、鎬を意識した剣道を取り組むことで必ずや剣道の幅が広がってくるはずです。(受付日:令和6年10月8日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。