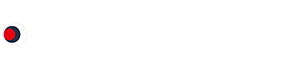図書
『令和版剣道百家箴』
「継統は力」
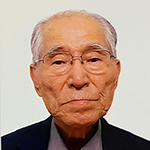
剣道範士 渡邊 哲也(東京都)
私は昭和18年4月1日熊本県菊池市雪野(元菊池郡龍門村雪野)の農家である渡邊家の4男として生まれました。当時は戦時中で田舎の暮らしはまだまだ厳しいものがありました。特に渡邊家は経済的に苦しい中にありました。小学校には満6歳で入学しました。戦時中で生まれたのでクラスは55名1クラスでした。そして家庭では労働力の一員でした。学校に行く前に馬、鶏の餌やり、また部活を終え帰宅するという同じ毎日でした。農繁期は学校が休みで農家の手伝いでした。これは中学卒業まで続きました。剣道を始めたのは、中学2年の2学期、昭和30年です。野球部からの転部でした。昭和27年剣道が解禁になり、その号令を今か今かと待っていた北村先生が終戦直後の厳しい状況下、村長宅の蔵から、今のようにおしゃれな防具ではなく、竹胴でしたが、数組調達、修理され始まりました。道場なんてものはなく、小学校と中学校の間の空いていた2教室が道場かわりでした。
部員は何人いたか覚えていませんが、2年生は私が大将で3名、1年生2名で県大会に出場し準優勝し、3年生になり同じメンバーで優勝を狙いましたが、優勝チームに準決勝で負けてしまい3位でした。当時は郡市大会では優勝は当たり前で負け知らずの成績でした。
3年生時、当時進学組は英語選択をしていましたが、私は経済的に諦めておりました。3学期の三者面談で急に高校に行くことになり菊池農蚕高校に進学しました。
高校での戦歴は2年生時、3年生4名私が大将、のメンバーで西日本大会に1度だけ出場しました。優勝した福岡商業高校に2回戦に当たり、先鋒に副将まで負け、私の番で先鋒、次鋒まで勝ち、中堅の福岡で有名だった池田選手に一本負けをしました。
昭和36年3月、就職は、警視庁、神戸製鋼と合格していましたが、警察が剣道が出来るだろうと思い、警視庁に決めました。1年間の教養後、翌年37年卒業配置で城東警察に配置、江東区剣連が、火、金曜日が稽古会(当時は今のように市の体育館、道場はありませんでした。)でしたので、当番勤務以外は殆ど顔を出しました。三段でしたが区の代表で東京都剣連の大会に出してもらいましたが、審判に当時警視庁指導室の先生方がお出でになっていたと思います。警視庁は五段まで紫の面紐ですので、試合で認められ、昭和39年1月から対外選手候補15名に選ばれました。15名の中には、高校で、インターハイ、国体に出場した経験を持つ人が殆どで、その年は井(補欠の事)でした。悔しい思いをし、昭和40年1年間は、機動隊(38年11月、武道小隊に転勤)に所属していましたので、庭を挟んで隊舎があり、帰隊してから5階道場で毎日1,000本の素振りを1年間やり通し、40年には選手になりました。この年は森島先生が監督で、毎日1時間の切り返し、懸かり稽古で涙か鼻水かわからず同時に出て、親兄弟にはこの顔を見せられないな、と仲間達と話していましたが、良くついて行けたなと思い出しています。本当に年間を通じて厳しい毎日でした。1週間(土曜日は半日)毎日同じ訓練の繰り返し、基本稽古、懸かり稽古、切り返し、指導稽古に、互格稽古ですが自分は常に精一杯、稽古しているか、惰性で過ごしていないかと、反省し「日々新たなり・・・」という気持ちで取り組みました。
4月の合宿は鹿島神宮道場で、1週間朝夕小川先生を招いての座禅。禁酒でした。昭和52年4度目の全国警察官大会優勝。選手を卒業指導室勤務になりました。平成12年4月警視庁を退職し、関東管区營察学校に赴任しました。これから自分の稽古は出来なくなるなと思い、当時非常に個性がある剣士が多いと聞いていましたので、講談社の朝稽古会を思い出し、師範の森島先生の許しを請うて、午前学校の授業が無い日出席しました。打ち合いならば負けないが、構えと心の修行をしたいとの思いが目的でした。
ここで、「昭和の剣聖」と言われた持田先生の遺訓に出会いました。
『剣道は50歳までは基礎を一所懸命勉強して、自分のものにしなくてはならない。普通基礎というと、初心者のうちに習得してしまったと思っているが、これは大変な間違いであって、そのため基礎を頭の中にしまい込んだままの人が非常に多い。私は剣道の基礎を体で覚えるのに50年かかった。私の剣道は50を過ぎてから本当の修行に入った。心で剣道をしょうとしたからである。60歳になると足腰が弱くなる。この弱さを補うのは心である。心を動かして弱点を強くするように努めた。70歳になると身体全体が弱くなる。今度は心を動かさない修行をした。心が動かなくなれば、相手の心がこちらの鏡に映ってくる。心を静かに動かされないように努めた。80歳になると心は動かなくなった。だが、時どき雑念が入る。心の中に雑念を入れないように修行している。』
あの剣聖と言われた持田先生が基礎を体で覚えるのに50年かかったと言われています。私なんか一生かかっても、からだに覚えられないな、と思いました。しかし参考にしたいと強く思いました。
また、剣道の稽古は基礎を習得することにより応用が生まれ、応用を高く習得するにはより深く基礎を学ばなければならいとあります。いかに基礎が大切であるかが伺われます。
関東管区警察学校は、関東10都県(皇宮察を含め11チーム)の総元締めです。管内大会は、2年連続、警察執行務に2本目はないと言う事で団体戦を、反対意見もありましたが、1本勝負で行いました。剣道大会の前例で1本勝負の大会は見たことはありません。いい思い出として残っています。
警視庁、関東管区警察学校在職を通じて、(37年間)剣道修行に専念出来た環境に置いて頂いたことに、深く感謝を感じています。平成15年4月退職しその後、平成19年、新道場の落成に伴い、森島先生からご指名により、野間道場の師範になりました。
今の剣道は凄く技術面は高くなっていますが、手に汗して応援する試合は少なくなっているように思います。立ち上がりから、スピードとタイミングの試合が多く先を取るより受けから打突するような気がしています。蹲踞から立ち上がり、触刃の間、一足一刀の間から打ち間までの間合いの攻防が少ない気がします。立ち上がり打ち間(近間)にいて直ぐに打ち合いの試合が多く見受けられます。若いときはこれで良いと思いますが、年をかさねるとともに理合の剣道に移行することが必要です。これが日本伝剣道に通じて行くことだと確信しています。このことは「はっと思ったら負けと思え」とか、理合のことは森島先生に、ショッチュウ言われました。「今は当てっこが上手いだけだよ・・・」と。
間合の攻防は蹲踞から立ち上がり、お互いが遠間の状態から始まります。ここから、触刃の間、一足一力の間と間合を詰めていきつつ相手を崩していき、打突の機会を感じたら、直ぐさま打って出ることが求められます。特に攻めるとき左足のひきつけは重要です。剣先、間合は剣先が自分に遠く相手に近く自分はいつでも打てるけれども、相手は打つことの出来ない有利な打ち間を作り出します。「誘い攻め」と言う言葉がありますが、左足は右足に通常よりわずかに深く引き付けることで、剣先が5センチから10センチ程度詰まります。このわずかな間詰めを利用して相手を攻め崩し、盤石の態勢で相手が居つくのか、退ぞくのか、前に出て来るのかの反応を伺います。技は自分勝手に遣うのでなく、面に出てくれば、すり上げ面、出小手、居ついていれば面、退けば飛び込み面、相手の状態により遣い分けるのです。勿論常に、先の気がなければ通用しません。“後の先”と言う言葉がありますが私は”先の後”と言います。これは誘い攻めに通じるものです。後の先の技は決して相手の技を待って返すことではなくそれ故に“先の後”と表現しています。
少年剣道の人口が少なくなって来ているようですが、これは今、少子化問題で剣道だけではなく、他のスポーツクラブも同じと聞いています。この少子化問題は国を上げて取り組んでいます。全剣連の役員の方々はさらに知恵を出して頂きたいと思っています。日本剣道が、また世界の剣道が益々普及発展することをお祈り致します。(受付日:令和6年5月28日)
*『令和版剣道百家箴』は、2025年1月より、全剣連ホームページに掲載しております。詳しくは「はじめに」をご覧ください。