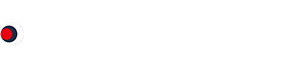図 書
剣術(道)歴史読み物
最終回 競技論から道の思想へ
―高野佐三郎述「三人制審判法」と富永半次郎著『剣道に於ける道』―
大阪大学 元教授
杉江 正敏
大正末期から昭和初期にかけて外来のスポーツが各種移入され、学生を中心として盛大に大会や対抗試合が行われるようになってくると、日本古来の武道のルールが他のスポーツと比較され、その適正化への提言が、これらの大会に携わっている人々によってなされるようになってきます。
先々回に述べましたように、武徳会の明治神宮大会不参加の表明にみられる「武道は勝負を争うことを本旨としない」とする見解に対し、西洋のスポーツの方式を加味して競技すべきであるという意見や、審判の位置によって判定が左右される一人制に対し、三人制審判の主張が行なわれます(『剣道の歴史』総論編「学生剣道の隆盛と剣道の必修化」などを参照下さい)。
これらの主張がある程度採り入れられ、昭和4年の御大礼記念天覧武道大会は、三人制審判法(主審の権限が重く三審平等ではない)が採用され、予選リーグの後、決勝トーナメントにより優勝者が決定することになりました。
1、高野佐三郎述「三人制審判法」
ここでは天覧試合の翌日に催された「剣道座談会」(『体育と競技』 8巻6号 4年6月)をとりあげ、審判の任に当たった高野佐三郎の談話を通じて、天覧試合で実施された三人制審判法についての論議を紹介します。大会の直後に行われたこの座談会は、試合の雰囲気を生々しく伝えています。特に高野が、三人制、多数決判定を好意的に受けとめているのが印象的です。
高野 あれ(三審制)は、熟練すれば良い審判法だと私は思ひます。今迄の審判法では一人で決るのですから苦情は云へないし、一人では神ならぬ人間のことですから、より困難な筈です。三人寄れば文珠の智慧と云ひますからね。あれはもう少し熟練するといい。三人一致する様になつて來ると良いですね。裏に聞くのだが、聞いてから勝敗を決めることは実際から云ふと出來ない。その瞬間の気分ですからね。※中略
今の三人でやる審判法は一ケ月程稽古しました。三人手を挙げるのに不揃ひだと陛下の御前、誠に体裁が良く無いですからね。
富永 一体その審判法は誰の創案ですか(※富永堅吾 当時東京高等師範講師 『剣道五百年史』著者)。
高野 西園寺さんです。あれは三人が一心同体でやらないといけないですね。表審判が手を挙げれば大概揃ふ様にありたいものです。
富永 一心同体なら主審はやりよいですが、三心三体の場合は大変なことになる、裏が表と意志が通じてゐない時は、審判しにくい場合が有るかも知れないですなあ。※後略
高野は、この方法の発案者は西園寺(※八郎 大会委員長 主馬頭 侍従職御用掛)さんと話し、初めてのことで随分苦労したが、熟練して三人が一心同体となれば「三人寄れば文珠の智慧」となり、これは良い方式であると結論づけています。当時斯界の第一人者である高野が、この三人制審判法に対して、発案者に対する気遣い以上に賛意を示した意義は大きいと思われます。しかし、瞬時に打突の判定が要求される剣道では、三人の表決が一致しないことが、次の打突の判定の遅れにつながり、富永の危惧した三心三体は、現今の試合においても散見されることがあり、三人が一心同体となって試合を運営することの大切さを痛感します。戦前の武道界において画期的な大会といわれる、この試合の反響は大きく、武道の社会的地位向上や競技化の進展につながり、ひいては学校体育の中で重視される要因の一つとなりました。
昭和6年(1931)9月の満州事変前後から、武道は国民教育の一つの柱として重要視され始め、6年1月の中学校令の改正により、剣道・柔道は必修化され、11年(1936)6月の学校体操教授要目の第二次改正にあたり、剣道・柔道の教授要目が初めて制定されました。
16年(1941)12月に始まった太平洋戦争の激化とともに、「実戦即応」型武道についての論議が盛んとなりますが、対米地上戦闘が本格化する18年以降、軍部のなかには武道の実戦的有効性を否認し、行軍・銃剣術・射撃以外の武道の実施さえ不要と主張する人々もありました。戦況が悪化した19年頃からは、剣道の試合や稽古がほとんど実施できない状況となりました(『剣道の歴史』総論編「戦時体制下の剣道」)。
2、富永半次郎著『剣道に於ける道』
前述の昭和19年に出版されたのが、富永(半次郎)の『剣道に於ける道』でした。混乱する世相の中、時代を超絶するかのごとき感のあるこの著述は、武道史研究の泰斗今村嘉雄(東京教育大学名誉教授)の編纂になる『近代剣道名著体系 第14巻』の掉尾を飾り、編者の解題では、
「著者富永半次郎は埼玉県の人。剣道の専門家ではないが、剣道を全く体験していない人物ではない。東京帝国大学の法学部、文学部に学び、文部省社会教育会主事、財団法人日本協会理事として、本書執筆時点で文部省嘱託二十年という、本大系執筆者としては最高の学識者の一人であり、著書や論文も多い。本書は、表題のように、剣道に於ける道とは何かを、技法よりも心法をとりあげて、文化史上での剣道を精神史的に分析して、武道人としての完成が人として国民としての完成と、どのように結びつくのかを問題として提起した。」と、最大級の賛辞がこの書に捧げられています。
この著書は私の研修時代「幻の名著」とされ、神田に日参して探し求めた本でした。これを手にした喜びは忘れられないもので、今でも、これを見つけた書店のどの棚にあったのかは、鮮明に記憶しております。
今思えば、『剣道の歴史』の執筆にあたり、総論編の「結び 武の理想と活人剣」で、夕雲の「相ぬけ」を提起した意識の底に、かつて読んだこの本の影響があったことは間違いありません。
富永は、序言において剣道を日本文化の一つと位置づけ、技法、刀法などの技術論ではなく、先人達が剣技を通じて何を学ぼうとしたのかを検討すると述べています。
この著で一貫して論じられているのは、「武」の理想が「相ぬけ」にあるにもかかわらず、表現できる「術」の完成型が「相討ち」にとどまるということではないかと考えます。著者は、夕雲流を次のように評しています。
「結局、夕雲流には一定の刀法としての型はなくなってしまいましたが、それは相ぬけを流とすれば、勢いそうならざるをえないのです。※中略 これがこの流がついに歪曲されたり、また一般に流行しなかった一つの原因をなしているゆえんであると想われます。」このため、弟子の小田切一雲は、「相討ち」が究極の目的ではないことを自覚しながらも、「当流兵法の意地は、元来勝負にかかわらず、取り分け余が思うところ、相討ちをもって至極の幸とす」と述べ、その「相討ち」に至る技法を提示せざるを得なかったのでしょう。
3、おわりに
南山大学教授榎本先生、天理大学教授湯浅先生から私にバトンが手渡され、15回にわたったこのシリーズも最終回をむかえました。この連載で剣道愛好家の皆様にお伝えしたいと努力したことは、われわれが現在修行している竹刀剣道はどのような理念と時代背景のもとに伝承されてきたのかということでした。
江戸期の平和な時代に成立した型と伝書による剣術の稽古は、近世芸道思想にささえられ、芸位の進展と人格の向上をめざした武士の表芸として位置づけられました。しかし、他流との技術の優劣をはかる具体的な目安がないことから、本来の「剣の真剣味」が薄らいできました。ここに登場した竹刀剣術は、他流試合を可能にし、競技として発展する素地を形成しました。
以後の論点は、この竹刀剣術がどれほど真剣味のあるものであるのかということと同時に、試合や競技を通じて、伝統的に主張されてきた修養としての価値をどのように伝承するかということにありました。
本シリーズの「修養論の系譜の1」でとりあげた山岡鉄舟は「春風館掲示」のなかで、
「苟(いやしく)モ剣術ヲ学バントスルモノハ、虚飾ノ勝負ヲ争フベカラザルナリ」
と説示しています。剣道において「虚飾の勝負」とは何をさし、「真の勝負」とは何なのかを明らかにしてゆくことが、競技としての剣道の発展につながり、先人達の業績に報いることになるのではないかと考えます。
(了)
*この剣術歴史読み物は、2002年5月〜2003年7月まで3名の筆者によりリレー形式で15回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。