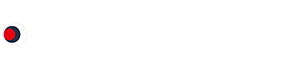審査会
更新
剣道七段審査会(福岡)
- 開催日:
- 2025年08月02日(土)
- 会場名:
- 福岡市総合体育館
審査会結果
審査員の寸評(実技)
令和7年8月2日(土)七段、3日(日)六段査会が福岡市総合体育館において実施されました。今回の審査結果は、七段は受審者560名で合格者120名、21・4%の合格率です。六段は受審者469名で合格者134名、28・7%の合格率です。見事七・六段に合格されました皆様、誠におめでとうございます。今回残念ながら思いが叶わなかった皆様にはさらなる修錬に努めていただきたく、私が担当した第4会場の所感を述べさせていただきます。
六段以上の審査方法の着眼点は初段から五段までに加えて、「①理合②風格・品位、さらに高度な技倆を総合的に判断し、当該段位相当の実力があるか否かを審査する」とあります。まず、立ち姿・着装が不十分で、礼法・所作が身についていない。特に袴の着付けで裾が後ろ下がりになっている。面の装着で物見が合わず顎が出た姿や面紐をかなり上部で結んでいる方、面紐の長い方が見られました。美しい着付け、正しく安全な装着こそ大事です。指導者の立場にもなります。着装と姿には常に留意していただきたい。
立合いは、その技量はもとより覚悟を示す場です。いざ、立合いを拝見すると、立合いの間での姿よく、油断なく落ち着いた礼、三歩進み蹲踞。ここに覚悟を感じます。「始め」で立ち上がり正中線を攻め、崩し、機をとらえて打ち切る(捨てる)、残心となり即、次に繋がります。これが高段者の剣道と評価されるところです。逆に不合格の方は、攻め・崩しが無く我れ先にと打ち出すのが早く、攻防が無く相手の状況を感知することなく仕掛けるため、的確な判断と決断なく有効打突に繋がりません。上半身が力み、捨てきれないため、踏み込みが弱くなっています。性別や年齢・体力により間合いやスピード・強度は異なりますが、気剣体一致の剣道を目指していただきたい。そして、相手の鋭い打突に動じることなく構えを崩さず捌く、ここも段位相当の実力ということになります。平素から、気で攻めて、理で打つ、肚で打つ、を心がけて、一層精進されることを望みます。
最後になりましたが、今回合格された方の一層の精進と真の七・六段の実力をつけられ、それぞれの立場で剣道発展のためご活躍を祈念申し上げます。
審査員の寸評(剣道形)
例年に無い猛暑の中、8月2日(土)・3日(日)に福岡で開催されました七・六段審査会で剣道形の審査を担当しました。その結果と所感を述べさせて頂きます。先ず合格されました皆さま方に心よりお祝い申し上げます。ただ残念なことは、七段で1名、六段で3名の不合格者が出たことです。そこで受審者の方々を拝見しておりますと、一体何の為に昇段審査において初段から最高段の八段迄に必ず剣道形の審査が科目として入っておるのかを理解しておられない方が、多数見受けられました。ただ審査があるから、兎に角形だけ、順序だけ間違えない様に稽古してきたと感じました。
剣道形が審査科目として含まれるのは、何故なのか?
「剣道形八徳」にも
一、形の修錬によって旺盛な気力の充実、心身を錬ることで呼吸法が会得できる。
二、所作、礼法を身に付け、物事を冷静に判断する心を養う。
三、稽古の悪癖の矯正で正しい刀の使用法が身に付く。
四、間合と理合、打突の機会が身に付く。
五、気品、風格、気位が生まれてくる。
等々、竹刀稽古と形稽古を車の両輪として修錬することの重要性を古来より言われておることと、お考え頂きたいものです。
又『日本剣道形解説書』の中で、10項目の審査上の着眼点が掲げられております。これらは、いずれも剣道形を修錬していく上で大切な項目ばかりであります。是非形稽古の指標とし更には、各本毎に、それぞれの流れを、打太刀・仕太刀を対比しながら説明してあり、非常に分かり易い『剣道講習会資料』を熟読吟味で剣道形の習得に努められまして、正しい剣道形が伝承出来る指導者を目指して自己研鑽を御願い致したいものです。
行事概要
- 行事名
- 剣道七段審査会(福岡)
- 開催日
- 2025年08月02日(土)
- 会場名
-
福岡市総合体育館
〒813-0017福岡市東区香椎照葉6ー1ー1
JR鹿児島本線『博多駅』より 『博多駅』 → 約8分 → 『千早駅』下車 西鉄バス『千早駅前』行先番号[1][快1] → 約15分 『福岡市総合体育館』バス停 → 徒歩 約1分