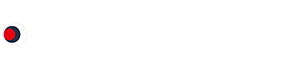図書
段位審査に向けて
最終回 真砂 威範士に訊く(「段位審査に向けて」の総括)
この企画は、広報委員会委員長の篠原政美氏を中心としたスタッフが、実際に六段から八段までの段位審査の審査員を務められている先生方の生の声をインタビュー形式で段位審査合格の要点を聴き取りまとめたもので、令和3年5月号から18回にわたって連載してきました。
段位は、剣道の技術的力量(精神的要素を含む)について付与基準に該当する者に与えられるものですが、その要諦を今まで18人の範士にお話しいただきましたが、段位審査合格に向けての要諦はほぼ網羅されていると思われます。
インタビューの中味で一番多かったのは「攻め」についてでありました。蛇足になるかも知れませんが、私が考える「攻め」の要点について述べさせていただきます。
「間合」と「攻め」について
剣道において「間合」は非常に大切な要素です。剣を交えた対者との間合が接近すれば自ずと緊迫度が高まります。緊迫度が高まれば、恐懼疑惑の「四戒」が生じ、力んだり、焦ったり、逸ったりする心の症状が現れやすくなります。
両者が相対峙し、切迫した間合での攻め合いのなか、「相手を見る存在」でいられるか、それとも「相手に見られている存在」になるか、によって優劣が決まります。
仮に「相手を見る立場」をA、「相手に見られている立場」をBとすると、正に「優勝劣敗」、Aが機先を制し、Bは引けを取ることとなります。
緊迫度が高まったなかBは、先んじて打って出るか、間合を切るか、さもなくば我慢して耐えるか、いずれにせよ不利な情勢やむなしです。
当然、強者と弱者が対すれば、強者がAで弱者がBになること必定です。しかし、両者の実力が拮抗する場合でも、せめぎ合いのなかで、どちらがAの側に位置し、どちらがBの側に落とし込まれるかで勝敗が分かれます。ここに剣道が「心の戦い」と言われ、また「打って勝つな、勝って打て」との指導が、今もって厳然と行われている所以であります。
Bとしては、間合を切っても所詮一時しのぎに過ぎず、いずれ捉まるでしようし、また我慢して踏み止まれば心身がこわばり、身動きが取れなくなります。否応なくBは、先に打って出ざるを得なくなります。そこに打突の好機、技の「起こり」が生じます。起こりをとらえる技を「出ばな技」と言いますが、これは相手に先手を出させ、その先を越すものです。
「先」の本質
よく「先手必勝」という言葉が使われますが、剣道の場合、先に技を出すことが必ずしも先とは言えません。Aのように、心を鎮め観察眼をもって相手に技を出させるように圧する働き掛けこそが先の本質だと思います。
攻め負けたBが「遅れまい」と急ぐゆえに心身の不一致によるギコチなさが「起こり」となり、Aがその「出ばな」をとらえる、というのが勝ちの本道です。
少し古いのですが、大相撲の元横綱、稀勢の里(荒磯 寛)が『文藝春秋』(令和元年12月号)の取材に応えた言葉の中で一番目にとまったのが〝先に立ったら負け〟でした。
立ち合いについて述べているのですが、本文をそのまま引用いたします。
「常識的には、相手よりも最初に勢いよく立った方が優位とされています。違います。相撲では、先に立った人間の負けです。強い力士は、それが分かっているから相手を先に立たせる。白鵬関はどっしりしたイメージそのままに、相手を先に立たせます。仕掛けが速いと思われていた日馬富士関、体が小さく機敏な鶴竜関についても、立ち合いでは後から立っています。」
まさに剣道の立ち合いも同じです。
前述のAの圧力に負けたBが、遅れまいと急ぐがゆえ心身にアンバランスを来たし一瞬の起こりを生じさせる。
ゆったりと受けて立つというのが「横綱相撲」と思いがちですが、実は、実力に裏打ちされた自信と気迫に満ちた偉容が、相手に負の心理作用を引き起こさせるのでしょう。
対者は「先に立った」のではなく「先に立たされている」のです。
さきほどA対Bで「相手に技を出させるように圧する働き掛けこそが先の本質」と申しましたが、攻めについて、相撲にも剣道と通底する理合があるものだと感じたしだいです。
このA対Bにおいて、いかにすればAの立場をとることができるか、またBに陥らずにいられるか。これはケースバイケースなので、攻め合いの場面を逐一言語化することは難しいですが、「一触即発」「間一髪」の機にいかなる心境や態勢にあるかが肝心です。常に「相手を見る立場」で対峙することを心がけ修錬に励んでください。
いよいよ今年も秋の段位審査のシーズンに入ります。できるだけ沢山の方が合格されるよう祈念いたしまして、インタビュー企画「段位審査に向けて」の総括とさせていただきます。
*段位審査に向けては、2021年5月号から2022年11月号まで全19回に渡り月刊「剣窓」に連載したものを再掲載しています。役職は、掲載当時の情報をそのまま記載しております。